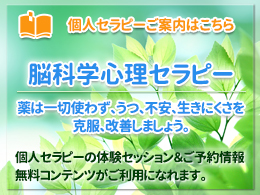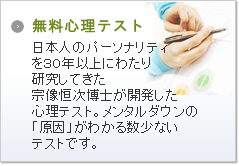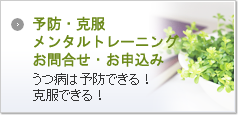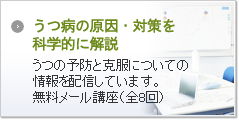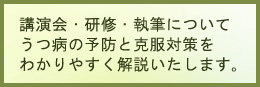企業メンタルヘルスご担当者向け情報「医師すらも納得する、脳科学メンタルトレーニングのストレス診断テストの特徴とは」
先日、脳科学メンタルトレーニングの開発者で、当研究所の長年のアドバイザーである、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が、医師向けのメンタルヘルスセミナーを行いました、
内科医、脳神経医、産業医、歯科医師、の合計7名の医師が集まり、私もスタッフとして参加しました。
エビデンスや理屈にうるさい医師たちを相手に行うメンタルヘルスセミナーは、他にはない脳科学メンタルトレーニングの大きな特徴だと思います。なぜこんなことが可能なのかというと、何度も書いていますが、脳科学メンタルトレーニングは、慢性ストレスが脳、免疫、内分泌、遺伝子発現、などに与える、生理的客観的データについて科学的に研究されているものであることが非常に大きいと思います。
やはり相手は医師ですから、いい加減な理論では納得させられないのですね。
そして、もうひとつ大きな理由があります。それは、その場で実施したストレス診断テストの数値を、セミナー終了後までには、確実に改善してしまう、ということです。
何をすれば、メンタルヘルス不調の原因である慢性ストレスが実際に解消してしまうのか、ということを、医師たちに身を持ってその場で体感させてしまう、ということです。
先日、ストレス診断テストの義務化の法案が通りましたが、現在皆さんの企業に営業してくる営業会社が持ってくるストレス診断テストは、そこに現れたストレス度を確実に改善させる方法がないと思います。
今あるストレス度はどの程度か、を測定することはできるでしょうが、それを確実に改善するにはどうしたらよいか、という解決策がないと思います。
現在、政府が検討しているストレス診断テストも、10項目前後のもののようですが、これも現在のストレス度は測定はするでしょう。しかし、なぜそうなるのか、何をすればその数値は確実に改善できるのか、という方法論や解決策はないと思います。
たぶん、お医者さんのところへ行って、当面休職して薬を飲んで、カウンセラーにすこしお話を聴いてもらってください、という指導になるだけと思います。
それはよいのですが、せっかく行ったストレス診断テストの結果
が変わることろまで誰もが責任を持って指導するということをしな
いのです。それはある意味仕方のないことと思います。
彼らはその数値を確実に変える方法を研究してきているわけではないからです。
解決策がないストレス診断テストを行うことの最大のデメリットは、社員がその診断テストのことを信用しなくなり、本当のことを書かなくなる、ということではないかと思います。
なぜなら、何をすればこの診断テストの数値が解決できるのか、ということがはっきりしない診断テストをやらされる側の心理を想像してみると、それは容易にわかるのではないでしょうか。
本当のことを書くだけ損しませんか?
実際、多くの企業のメンタル担当者に会うと、ストレス診断テストをやるのはやめたとか、やっても社員が本当のことを書いてくれないので意味がない、と言っている方がたくさんおられます。
それはそうだと思います。どうすればこの得点を改善できるのかがわからないものをやらさせても、やらされる側としても「これをやってどうするの?」と思うのではないでしょうか。
しかし今後、義務化されるにあたり、とりあえずやらなければいけないということになると思いますが、そもそも社員の手をわざわざ煩わせてまでこれを行うのでしたら、どんな診断テストを行うのが最も社員や会社のためになるのか、という判断が重要になるのではないかと思います。
義務なんだからとりあえず何でもいいからやっとけば良い、とう考えで行うのだとしたら、その先に待っているのは、社員の以下のような反応ではないかと思います。
「本当のこと書いても意味ないから、適当に書いとけばよい」
これでは、やらせる側もやらさせる側も労力だけかかるだけで、むなしいことになってしまいますね。
ストレス診断テストの結果を確実に改善できる解決策を持っっている、診断テストを検討されることをお勧めします。
脳科学メンタルトレーニングのストレス診断テストに関心持っていただける方は、以下から資料をご請求ください。
2014/07/29
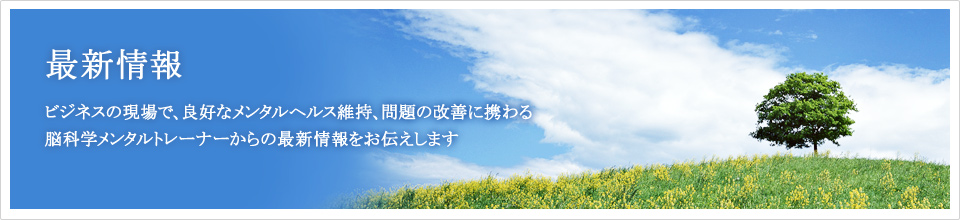
 前へ
前へ