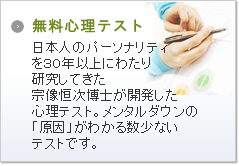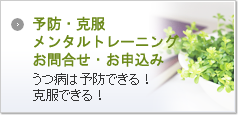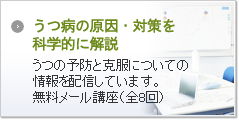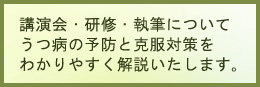企業メンタルご担当者様向け情報「NHKスペシャル”キラーストレス”で、解説されていないあるポイントが分かると、うつ、メンタル不調を作る慢性ストレスは解決できる」
<お知らせ>
山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/14発売! リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
<ここからブログ>
今年の6付にNHKスペシャルというテレビ番組で「キラーストレス」というテレビ番組が放送されたり、SMAPの中居 正広君が司会を務めるテレビ番組「金スマ」でも、キラーストレスの特集が組まれたこともあって、今やキラーストレスは多くの方々の知ることろとなりました。
ところで、NHKスペシャルではストレスが発生する仕組みを詳しく解説していたのですが、ある重要な1点が説明されていなかった、ということをお気づきだったでしょうか。
NHKではこう説明されていました。
「ストレスが発生すると、まず最初に脳内の扁桃体(へんとうたい)が反応し、その後、全身にストレス反応が引き起こされる」
この説明の中に答えがあります。それは、
情動の発電装置である扁桃体は、「なぜ反応するのか」、という理由が説明されていないのです。
これがわかればもっとも根源的な対策が取れるのではないでしょうか。
「ストレスが発生すると、ます扁桃体が反応し・・」と説明されると何となく、ふーん、そうなんだ、という理解になりやすいのですが、よくよく見るとここが説明されていないのです。
また、NHKスペシャルの2日目に出てきた早稲田大学の教授も、こんな風に言っていました。
「うつは、扁桃体で作られるのですが・・・」
同じように、「なぜ、作られるのか」については、説明されていないのです。
弊社顧問である、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士は、ここを研究したのです。なぜなら、これがわかれば、うつ、メンタル不調の原因・対策を突き止められるからです。
そして、わかった原因は、以下の通りです。2点あります。
1.扁桃体は、相手の表情、声に敏感に反応する。そこから慢性ストレスは作り出される。
御社で慢性ストレス状態に陥っている人に、次のような質問をしてみるとよいでしょう。
「職場には、あなたが怖いと思う表情をした人はいますか?」「あなたが怖いの感じる、音や声は職場に飛び交っていますか?」
まず、ほとんどの人がイエスと答えるでしょう。
扁桃体は、自分の意思に関係なく反応しますから、いくら休職しても扁桃体の感受性を変えないまま、復職させても再発を繰り返すだけでしょう。ほとんどの企業は、再発を繰り返していませんか?
うつや、メンタル不調は、繰り返すものだみたいに感じている人も多いかと思いますが、私たちはそうは思っておりません。なぜなら、私たちがかかわった某上場企業では、3年半、初回鬱で休職した人の再発率は0%という結果でいるからです。
扁桃体の表情や音に反応する対策をしっかり取るかどうかが重要だと考えます。
2.扁桃体は身体感覚に反応します。
うつ、メンタル不調を作り出す慢性ストレスを抱えている人は、例外なく全身に強い緊張やコリを持っています。
片頭痛や、肩こり、腰痛、胃の痛み、など。詳しい説明は省きますが、扁桃体は身体間カウによって興奮するのです。結論を言えば、身体感覚を良好化すれば、扁桃体興奮は静まり、慢性ストレスは消失するのです。
この身体感覚は何によって引き起こされるかというと、非言語信号によって引き起こされます。
それは、空間の広い狭いという皮膚感覚、熱い冷たいの温度感覚、暗い明るいの明暗、湿度が高い低いという感覚、におい、皮膚感覚、など。
よく電車に乗れないなどという人がいますが、これは空間の広さ狭さに身体が反応して扁桃体を興奮させているのです。
よって身体感覚を良好にして、扁桃体興奮を鎮めると電車が怖い、というような慢性ストレスは消失します。
また、曇りの日に起き上がれないなどという人もいます。これは、明暗に身体感覚が反応して、扁桃体を興奮させているのです。
私はこういう人を何人も扱ったことがありますが、曇りの日に感じる身体感覚を良好化することで、慢性ストレスは解消し、起き上がれるようになります。
こんなふうに扁桃体は、反応しているのです。
そのために、マッサージとか、風呂とか、ストレッチとか、アロマ、とか、そういうものは一時的に効果があります。体がほぐれれば、気持ちよくなりますね。良いのですが、効果が一時的なのです。これだけでは、安定的に仕事を行うにはちょっと難しいのです。
よってこちらが行う方法は、身体感覚を継続的に良好化し、その効果を持続させる心理セラピーを行うのです。
身体感覚が良好化した状態を継続させるので、扁桃体が静まり慢性ストレスが消失するのですね。そして、自分でこれをできるセルフケア法を教えるため、再発を限りなく減らすことができるのです。
一般の皆さんでもやさしくできるセルフケア法は、私の新刊本にも解説していますので、お読みいただければ幸いです。
そして、本格的に御社に取り入れたい場合は、お問い合わせいただければ幸いです。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出すラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育」、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/09/14
企業メンタルご担当者様向け情報「9/14 山本潤一新刊本発売! うつ、メンタル不調を作る不安遺伝子をコントロールする法とは」
今年6月ころから書いてきた本が、9/14にやっと全国書店で発売されることになりました。
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 秀和システム
実は私自身は、リーマンショックのころ、仕事がゼロになり収入がなくなったことがあります。当時、まだ結婚2年目でしたので夜が眠れなくなり、将来を悲観して「死にたい」というような気持ちにさいなまされました。完全にうつ状態だったと思います。
地獄でした。
しかし、同時にそんな地獄のさなかにこういう気持ちもふつふつと沸いてきたのでした。
「自分自身がうつ、メンタル不調を改善するプロとして活動してきたのだから、こんな自分を今こそ救わないでどうする!!」と。
そして、あるときは真夜中の布団の中で、あるときは朝早く起きて、今までの知識とセラピーテクニックをフル稼動させて、自分自身に対してセラピーを行ったのです。
結果、ものの見事に、「重苦しい、死にたい気持ち」を消失させることができたのです。助かった! と思いました。
将来に対して悲観的な気持ちがなくなると、一気にとっても楽になります。状況は何も変わらなくても。
こうなれば第一段階は成功ですね。気持ちがだんだん前向きになってきます。そして次に私は妻といろいろ話そうと決めたのです。
結果的に私はこれで完全復活を遂げることができました。何を話したかは、これ以上書くとネタバレになってしまうので、よろしければ本でお読みください。(笑)
何が言いたいかというと、一定のやり方で情動の発電装置である扁桃体興奮を鎮めるセラピーを行うと、うつ、メンタル不調を作り出す慢性ストレスは消失させることができる、ということです。
私自身が自分に行ったさまざまなセラピーテクニックで、一般の方々にも使っていただけそうなものをこの本にまとめました。
よろしければ、セルフケア教育、などにお使いください。
また、実践的なラインケア教育、セルフケア教育を行った見たいという場合は、お問い合わせください。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出すラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育」、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/09/04
企業メンタルご担当者様向け情報「SMAP中居くんの”金スマ”、でも特集された、キラーストレストレス科学の側面からの3つの対処法とは」
先日、8月26日(金)にSMAPの中居正広くんが司会をしている、「金スマ」というテレビ番組で、「キラーストレス」と言う特集が放映されました。
キラーストレスとは、命を脅かすようなストレスのことで、今年6月にNHKがスペシャル放送で「キラーストレス」という番組を2夜連続で放送してから、この言葉に注目が集まってきたものです。
NHKの放送では、「ストレスがあると一番最初に扁桃体が反応し、ストレスホルモンが分泌し、自律神経の興奮が表れる」とか、同番組に出演した大学教授が「うつは扁桃体にで作られる」という解説をしていたせいか、
番組放送後、「扁桃体にダイレクトに働きかけて、その興奮を鎮めて慢性ストレスを解決する、世界でおそらく唯一の心理療法」を行っている、弊社に対して非常に多くの、うつ、メンタル不調に悩む方々から、お問い合わせをいただいたのでした。
NHKの時は学術的な放送内容だったのですが、今回、金スマで放送されるとは正直びっくりしました。なぜなら、一般大衆向けの娯楽番組ですからね。キラーストレスのことを、たぶん多くの国民が知ることになるだろうなあ、と思ったのです。
番組内では、結婚や引っ越しなどのライフイベントが重なると、強いストレスになる、と解説されていました。
キラーストレスについて、弊社が行っているストレス科学の面から、考えてみたいと思います。ポイントは3つあります。
ポイント1 「感情を抑圧する傾向が強い人がキラーストレスに見舞われやすい」
心理学的な面から解説すると、「自分のあるがままの感情を抑圧しすぎる人」は、どうなるかというと、周りの目を非常に気にする人であり、非常に我慢をする人でもあるため、自分自身のキャパを越えると、突然、ボキッと心が折れるということです。
この傾向は、弊社顧問の筑波大学名誉教授。宗像恒次博士が開発した「自己抑制型行動特性尺度」で測定することができ、この得点が11点以上取ると、この心理傾向が強まることがわかっています。
対策は、「自分自身の感情を感じる練習を積むこと」です。感情を抑圧している人は、自分の感情がわからない人が多く、それゆえストレスの蓄積を自覚できない人が多いのです。
感情を感じる練習を積むことが、キラーストレスに対するセルフケア対策になります。
ポイント2 「不安遺伝子の制御法を身に着ける」
遺伝学的に言うと、不安遺伝子を持っている人がキラーストレスを発症しやすいと思います。日本人は、不安遺伝子(別名・損害回避遺伝子)の中でも、特に不安になりやすい気質を作ると言われる、SS型不安遺伝子を持っている人が非常に多いのです。
SS型不安遺伝子を持つ人は、パニックになりやすく妄想的な認知に陥りやすいことから、ライフイベントがいくつか重なると、キラーストレス状態になりやすいと考えられます。
対策は、たとえば弊社がもつ、不安遺伝子の発現状態を調べる簡易テストを行うこと。そして、その対策法を学ぶことです。
対策の一つを挙げると、SS型不安遺伝子を持つ人は、スキンシップされると落ち着きを取り戻しますので、スキンシップをしてくれる親密な人間関係、パートナーシップを持つ事が一番の対処法です。
パートナーがいない人は、そういうスキンシップをしてもらっているという、イメージワークをする事でも大丈夫です。
ポイント3 「扁桃体興奮を鎮めること」
脳科学的に言うと、パニックになりやすい人とは、脳内の情動の発電装置である、扁桃体が非常に敏感で慢性的に興奮しやすい人が、キラーストレス状態に陥りやすいと思います。
扁桃体が敏感な人とは、ちょっとしたストレッサーがかかると、パニックになりやすいのです。扁桃体興奮とは、身体的な緊張、違和感によってつくりだされるため、パニックになりやすい人とは、身体が非常に緊張しやすい人ともいえます。
簡易的に自分でできる対策とは、身体を緩めるセルフケア法を身に着けることです。身体を緩めるというと、マッサージなどがすぐに思い出されるとおもいますが、これでは瞬間的に効果は消えてしまうので、こちらのおすすめでは、簡易的なイメージワーク法をお勧めします。
扁桃体は、一定のイメージワーク法によって鎮静化させることができるからです。とくに光イメージを使ったイメージワーク法により、扁桃体は劇的に鎮静化することが可能です。
自分でやる簡易的な方法は、一時的なものなので、それでもパニックが止まらない人は、弊社などが行っている扁桃体興奮を徹底的に鎮静化する、専門家による心理療法を受けると完全な対策になります。
キラーストレス対策について、御社内で取り組んでみたいと思われる企業のご担当者の方は資料をご請求ください。
、弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出すラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育」、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/08/29
企業メンタルご担当者様向け情報「うつ、メンタル不調を作るもっとも本質的なストレスの原因とは」
そろそろ多くの企業では、義務化されたストレスチェックの結果が出始めてきているころかもしれませんね。
高ストレス者の判定がなされていることでしょう。
ところで、このメルマガを読んでおられるあなたは本当のストレスとは何によってもたらされるのか、といことをご存知でしょうか。
結論と言うと、それは、
「あるがままの自分を生かす生き方・働き方をしていないこと」から生み出されます。
上司が厳しいとか、残業が多いとか、そういうことはあくまでも副次的な事です。
あるがままの自分を生かせているかどうか、が一番のポイントです。
今、オリンピックが開催されていますね。選手たちはどれだけものすごい練習をするかお分かりでしょう。
甲子園が開催されていますが、選手たちはどれだけすごい練習をするのかお分かりでしょう。
なぜ彼らは大丈夫なのでしょうか?
それをすることが、自分自身に「合っている」と思えるからです。それをすることが喜びだからです。
ここまですごいたとえでなくても、あなたもわかるのではないでしょうか。
「これだ!」と思える生き方・働き方をしているとき、多少の困難はどうってことないのはないでしょうか。
自分らしい生き方をしている、自分はよい生き方をしてる、と思えれば、残業が多いとか、上司が厳しいとかは、どうってことない、そういう経験は多くの方がすでにしていることでしょう。
高ストレスかどうかだけで判断するのは、ストレス科学的に見て、あまり効果的ではないと感じます。
それよりも、「あるがままの自分を生かす生き方、働き方をしているかどうか」の度合いを見たほうが、より本質的・実用的と思います。
弊社顧問の筑波大学名誉教授が開発した行動特性尺度に、自己抑制型行動特性尺度というものがあります。
これは、自分自身の本音の気持ち、感情を表現できている度合いを見ていますが、この本質は、「あるがままの自分を表現する生き方・働き方ができているか」を見ます。
20点満点ですが、日本人の平均点は9点です。7点以上取ると、あるがままの自分を表現する生き方がだんだん乏しくなってきます。
平均的な日本人は、あるがままの自分を生かす生き方、働き方をしていないことになります。
ビジネスマンの幸福度を国際比較で調べた調査がありますが、日本人ビジネスマンの幸福度は非常に低いのです。
この心理テストが11点以上取ると、メンタルが非常に揺らぎ、15点以上取るとうつになってもおかしくない、というレベルであるという科学的研究がなされています。
それはそうだと思いませんか?
この心理テストで高得点をとるとは、あるがままの自分の気持ち、感情を抑圧する度合いが高いということだからです。おかしくなって当然でしょう。
企業は、そして上司は、部下の「あるがままの個性を生かす働かせ方」をさせればよいのです。
部下のあるがままを引き出すスキルを身に着ける事が重要です。
それこそが、最良のメンタル予防策、であり、モティベーション向上策だと思います。
こういう働かせ方をさせない企業で、メンタルが重症化しダウンするので、あとは薬を飲ませて休ませるしかない、ということになるのです。
あるがままのその人を生かす働かせ方をさせれば、元気が出てくる。
こういうことは、人事部でも企業トップでも経験的にわかることです。
こうしたことを自律的に考えられる人事部企業トップであることが、非常に重要なことなのではないでしょうか。
そういう意味では、自律的な判断をせず、医者の判断に過度に依存している企業は社員のあるがままの個性を生かす、ことがメンタルの本質的な対策だ、という視点を持つことが難しいかもしれません。
しかし、視点を大きく変えれば、それは可能です。
今、経済産業省では「おもてなし企業選」という、社員に愛され、顧客に愛され、地域に愛されている全国の中小企業を表彰していますが、こういう企業は離職率が少なく、メンタル不調者も少ないのです。
なぜかはおわかりですね?
そうです。社員のあるがままを引き出す、という働かせ方をしているからです。
厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出すラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育」、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/08/16
企業メンタルご担当者様向け情報「健康経営の重要ポイントが見えると、うつ、メンタル不調も解決のヒントが見える」
ここ数年、健康経営、と言うキーワードが脚光を浴びていますね。東証では、健康経営銘柄、という企業を指定して健康経営に力を入れている企業がメディアに紹介されるなどしていますので、だんだん認知度が高まってきました。
もともと健康経営とは、弊社顧問の筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が、1994年にロバート・ローゼンが執筆した「ヘルシー・カンパニー」という本を日本語に翻訳したあたりを草分けとして、以後、少しづつ認知が広まってきたように思います。
ちょうどそのあたりから、私も宗像博士の元で健康心理学び始めたのです。
その視点で言うと、私たちが考えている健康経営とは、昨今の健康経営とは少し違う視点がありますので、ご紹介したいと思います。
昨今の健康経営は、健康診断を早めに受診しましょう、と言うものが多いように感じます。でも、これだけだと、たぶん、企業はコスト増になってしまうだろうと私たちの立場からは考えます。
なぜか。結論を言うと、健康とは、病気がないこと、ではなく、病気があるなしにかかわらず、精神健康度が高い、生き方、働き方をしているかどうかを指すからです。
ご説明します。
もともと病気とは、健康心理学の定義では、「かかる病気」が多かったのです。たえば、伝染病とか、ウィルス性のものとか。これは、検査すればすぐわかりますから、薬を投与するなどして、対処法は明確でした。
しかし、昨今では「かかる病」より、「自ら作り出す病」が多いのです。これはストレス性のものがそうです。生活習慣病、がその代表例です。あと心因性のものものもそうですし、メンタル不調もそうです。
これらの病気は、検査しても原因が見つからないことが多いのです。それはそうです。ストレス性のものですから。かりに見つかったとしても、再発しやすいのです。
ストレスが原因で病になっていますから、症状を消しても、ストレスがたまりやすい生き方溜まりやすい生き方、働き方をしている限り、また症状は再発リスクがあるのです。
メンタル不調などはまさにその代表例でしょう。
これにしっかり対処するには、今ストレスがたまっているかどうか、と言うことではなく、ストレスがたまりやすい生き方、働き方をどう変えるか、と言うことなのです。
具体的に言うと、「周りに認められたい」という生き方・働き方をやめ、「たとえ周りに求められなくても、自分が満足できる生き方、働き方」に変換する、と言うことになります。
健康心理学では、前者の生き方・働き方を、他者報酬追求型人生(労働)、と言い、後者を自己報酬追求型人生(労働)、と言います。
今まで私たち日本人は、周りに認められたい、という強烈に強い欲求に突き動かされて、生き・働いてきたのです。高度成長期まではそれでよかtったです。
しかし現代では、認められたいと思っても、ポストが十分あるわけでもないし、賃金が必ずしも上昇するわけでもないし、リストラされるかも知れないし、要は「認められない」事が多いのです。
周りの評価をものすごく気にしたプロ野球・清原選手は、現役引退後、ものすごく太りましたね。メタボにもなった。認めてもらえないというところから来るストレスを癒すために、暴飲暴食に陥ったと私は推測します。メンタル不調にも陥ったでしょう。
一方、イチロー選手は、周りの評価を気にしているでしょうか。そもそも周りの評価は、自分ではコントロールできないものです。イチロー選手は、「コントロール出来ないものには、フォーカスしない」を貫いている人です。
イチローは、メタボにはなりませんね。
周りに認められたい、という欲求は日本人いものすごく強いパーソナリティですが、21世紀にもこれを持ち続けると、ストレスが原因の病(=自ら作り出す病)になっていくのです。この生き方・働き方を変えないままに、健康診断だけを早めに行っても、結局は病は再生産され続けることでしょう。
すると、結局は企業はなんどもなんどもコストを支払うことになり、無限のコスト増になるのではないでしょうか。
メンタル不調対策は、まさにこの状況に落ちいているのではないでしょうか。うつは何度も繰り返していますね。そして、結局は、繰り返す人を会社から追い出すことしか、対策はなくなってしまうのではないでしょうか。
実際、そういう企業は多いかもしれませんね。
話を戻すと、生き方・働き方を変える支援技術が必要なのだということです。
もともと弊社が行っている心理療法は、産業保健スタッフの方々に身に着けていただくための、行動変容支援の技術として開発されたものです。現在も、宗像博士指導の下、約1000人以上の産業保健スタッフがこれを学んでいるのです。
生き方・働き方を変える、支援をするものです。
そのことで、本人の慢性ストレスを解消し、結果としてメタボや生活習慣病や、その他、メンタル不調を含む、ストレス性の病を改善していくための支援技術なのです。
周りの評価を気にする生き方は、常に不安や怖れを根底に持っています。認められるだろうか、認めてもらえない。アップダウンの激しい生き方です。力にない人は、ずっと落ち込んだままになります。
これがメンタル不調です。
一方、周りに認められなくても自分で自分を認められる生き方・働き方は、自分が最低限評価できる、喜びのある生き方・働き方になるので、前者よりもストレスがたまらないのです。それどころか、自分の中に喜びのエネルギーを燃やし続けながら生き、働くことができるのです。
こういう視点で健康経営をとらえると、精神健康の高い生き方・働き方ができることがお分かりでしょう。これが本体の健康経営なのではないかな、と健康心理学では考えるのです。
自然とメンタル不調も改善されていくことがお分かりいただけると思います。
厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。
健康心理学に基づく個人カウンセリング、ラインケア、セルフケア教育、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/08/03
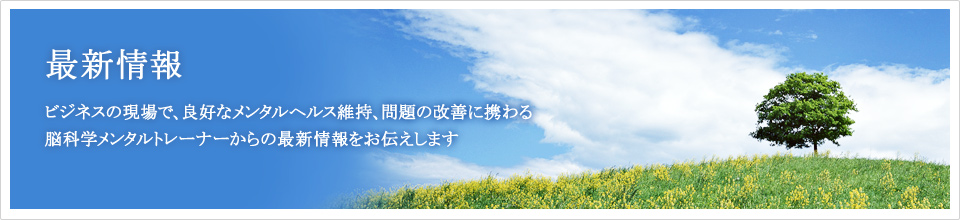
 前へ
前へ