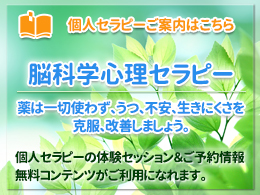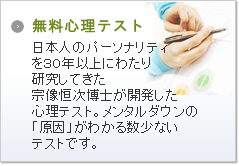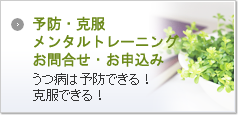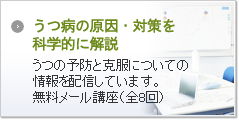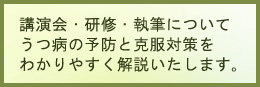企業メンタルご担当者様向け情報「発達しょうがいのことをよく知れば、上手に付き合うことができる」
<お知らせ>
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受けました。11/28号に掲載されるようなので、もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/14発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
先日、弊社顧問である筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が行った「発達しょうがいセミナー」に参加しました。非常に目がうろこの内容だったので、要点をまとめてお伝えします。
最近、企業でもこの問題に頭を悩ませている人事ご担当者も多いと思うので、お役にたつと思います。
まず、発達しょうがいは、日本では「発達障害」という漢字で表記されることが一般的ですが、実はこの名称、大いに疑問が残る名称です。
英語では、Developmental Disorder と書きますが、Disorder には、そもそも「障害」という意味はないのです。無秩序とか、混乱とか、そういう意味です。
宗像博士曰く、発達症、とでも訳すのが正確ではないか、とのこと。一般的な人から見たら「無秩序、混乱」に見えたとしても、たとえばエジソンはADHDだったといわれていますし、ウィンドウズを作ったビル・ゲイツは、自閉症スペクトラムであったと言われています。
これらの方々は、一般的な人から見たら「無秩序、混乱」している変人と見えたかもしれませんが、それは常識的な人から見たら変わった人に見えたから変人というレッテルを貼ったのであって、人々の多様性に対する理解になさから生まれてきている言葉なのです。
今的に言うと、ダイバーシティ(多様性)に対する無理解ですね。
つまり、発達しょうがい、とは個性と呼ぶべきものなのです。それを日本では、発達障害という漢字にしてしまい、いかにも「生涯変えることのできないハンディキャップを背負った人」「一生、医者の世話を受けて治療を受けなければならない人」「障害者」、ような間違った思い込みを多くの方々に広めてしまったのです。
こういう名称は誰が作ったのかわかりませんが、「発達障害」というレッテルを貼られた人が増え、生涯治療が必要と言われる人が増えることで、誰が儲かるのかを考えるとだいたいわかります。
話を戻すと、生涯変えられない性質、というのは全くの誤解です。
たとえば自閉症スペクトラムとは、相手の「目」を直接的に見ることができないことにより、周囲の人から「話を聴いていないように思われる」「反応がよくわからないように見える」「気の利いた反応ができない変わった人」「物事の同時並行処理が苦手」「人との距離感がわからない」
などの個性がその人にあり、周囲もどう扱ったらよいかわからない、ということになります。
相手の目を見れない、というのはここでよく紹介しているように、脳内の情動の発電装置である、扁桃体(へんとうたい)が過剰に反応してしまう、ということです。
扁桃体には、相手の顔に敏感に反応してしまう、顔反応性細胞がありこれが激しく反応して恐怖や不安やその他、さまざまなマイナス感情を発生させてしまうのです。
ほかのところで発達障害と言われ続けてきた人でも、私たちのところで扁桃体反応を安定させる心理療法を行うことで、相手の顔を見れるようになり、人との距離感が元に戻り、自閉症スペクトラムを診断する心理テストの得点が、標準値に戻った人はたくさんいるのです。
「障害」という名称は不適切だと思います。
多くの企業では、発達しょうがいと呼ばれている方々をどのように扱ったらよいのか、よくわからないというということもあるでしょう。
こういう方々との付き合い方の本や、そういうことを教えてくれる団体なども最近出てきていますが、一番見落とされているなと感じることが一つあります。それは、
「扁桃体にかんする配慮がない」
ということです。自閉症スペクトラムの方が相手の目を見るのを避けるのは、相手の表情を見てしまうと扁桃体が大暴走して、パニックが起きてしまうからです。
ADHDの人は、相手の表情に激しく反応して行動がしっちゃかめっちゃかになります。
特に自閉症スペクトラムの人には、目を見るコミュニケーションを期待してはいけないのです。このことがよく理解されていないために、一般に自閉症スペクトラムの人に対して行われる療育やソーシャルスキルトレーニングなどでは、相手の顔をよく見てコミュニケーションをするというような、訓練がなされることがあります。
これは逆効果で、扁桃体のことが知られていないために引き起こされる誤解です。
もちろん扁桃体興奮を鎮静化するという心理療法を行った後だったら大丈夫ですよ。でも、その前では逆効果です。
このことをよく理解したうえで、こういった方々と上手に付き合って生産性を高めるのコツがさまざまにあるのです。
ご興味ある方は、お問合せフォームからお問い合わせください。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/11/06
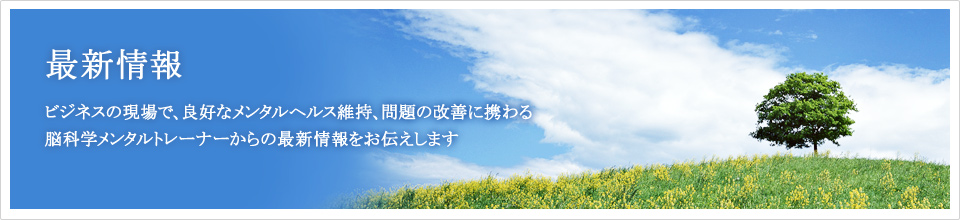
 前へ
前へ