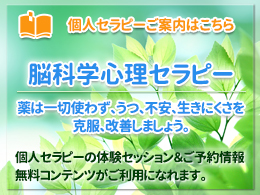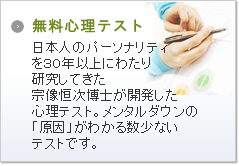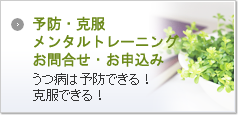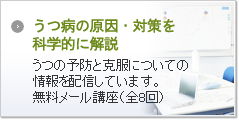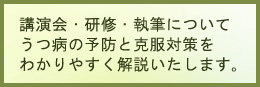企業メンタルご担当者様向け情報「チームを構築できる経営者、メンタル担当者がいると、うつ、メンタル不調は解決できる」
★6/25(日)13時~。「日本産業カウンセラー協会 神奈川支部総会」で山本潤一が講演します。テーマ→「脳科学心理療法のご紹介」。詳細決定次第、このHPでご案内します。
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
先日、3/22に厚労省が以下のような発表をしました。3/22朝日新聞デジタルによると、
「睡眠薬や抗不安薬、抗てんかん薬として処方される「ベンゾジアゼピン(BZ)系」という薬などについて、規定量でも薬物依存に陥る恐れがあるので長期使用を避けることなどを明記するよう、厚生労働省は21日、日本製薬団体連合会などに対し、使用上の注意の改訂を指示し、医療関係者らに注意を呼びかけた。」
「対象はエチゾラムやアルプラゾラムなど44種類の薬。BZ系薬は短期の使用では高い効果を得られるが、薬をやめられない依存性や、やめたときに不安、不眠などの離脱症状が生じることがあるとされる。日本では広く使われているが、欧米では処方が控えられ、長期的な使用も制限されている。」
とのこと。
44種類を見ると、よく聞くデパスやソラナックス、アモバン、ワイパックスなど、ほとんどのものが入っています。
ポイントは、「規定量でも薬物依存に陥る可能性がある」また、「やめたときに、不安、不眠、などの離脱症状が生じることがあるとされる」とのこと。
不安や不眠を改善するために使用しているのに、やめる時に不安や不眠などの離脱症状が生じるときがあるとか、まるで冗談みたいな話です。
また、「承認用量の範囲内でも、薬物依存が生じる。漫然とした継続投与による長期使用を避けること」と厚労省は注意しています。
承認用量を守っていても薬物依存に陥る可能性があるとすれば、もうこれは、医師と言えどもどうやってコントロールするのでしょうか?
また、「漫然とした長期使用」というのは、どう定義できるのでしょうか?
こういう答えが見えない問題は、メンタルの問題に関係なく、今の時代あらゆる分野に生じます。こうした時に、経営者やメンタル担当者がリーダーシップをとって判断していく企業は、メンタル問題に対し最善のアプローチができるのではないかと思います。
自ら判断するのではなく、医師などに丸投げしていると、なにも見えないかもしれません。
弊社とお付き合いしている企業で非常にメンタル対策がうまくいってる企業では、医師、産業医、我々のような心理士、にチームを組ませ、担当者がリーダーシップをとって、運営している企業です。
つまり、それぞれはそれぞれの得意分野、不得意分野があり、それを担当者がよく把握して、チームを組んで全員で問題解決する対策を取ってるのです。
うまくいかない企業とは、医師に丸投げしてる企業です。今回の厚労省の発表を見ればわかるように、承認用量を守っていても、薬物依存になす可能性があるとしたら、よほどのベテラン医師でないとまずは、その見極めはできないのではないでしょうか。
職人技、プロのカンの世界だからです。メンタルに関し、そこまでのプロレベルに達している医師は、そんなに多くないと言えるのではないでしょうか。
医師次第となると、もし本人が薬物依存になったとき本人はその医師を選んだ会社を訴える可能性があります、その場合、会社は医師を訴えることになるでしょう。
医師は、受けて立つ自信があるでしょうか? ある医師は少ないでしょう。
となると、現実的にこの問題の対処法を考えたとき、そこまで薬物を使わない対処法を考えることが重要ではないかと私は思います。よってこの問題を自主的に考え、対処するには経営者、メンタル担当者のリーダーシップが重要になるのです。
先の企業のように、そこまで薬を使わないとしたら、心理士を含めたチームとして対処していくことが重要ではないかと思います。それぞれの専門家を使い分けるには、経営者、メンタル担当者のリーダーシップが必要になるのです。
医師に丸投げしていると、これはできないのではないでしょうか。
今回の厚労省の発表は、こういう流れを加速する事になえるのではないかと思います。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
この心理療法や、これを使った予防法、教育法、復職支援、などにご関心ある方は、以下のお問合せフォームから資料の医師などとのチーム連携に関心ある方は、お問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2017/03/28
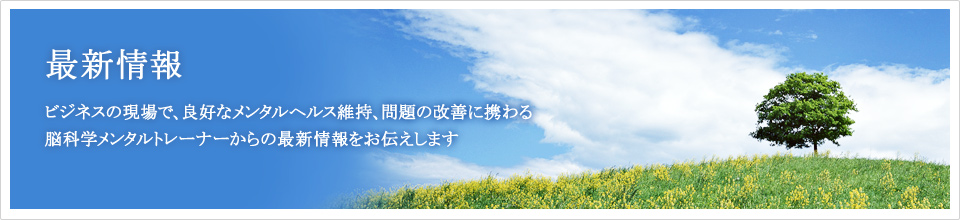
 前へ
前へ