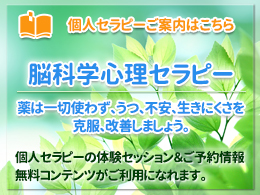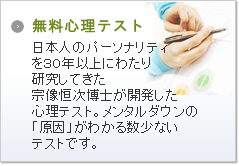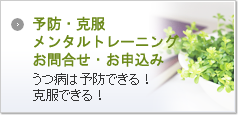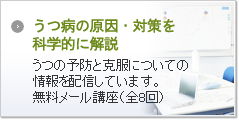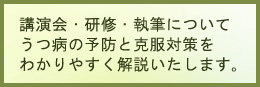企業メンタルご担当者様向け情報「"関係の質"を高めると、生産性は向上し、うつ、メンタル不調は解決していく」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
「関係の質」という言葉をご存知でしょうか。ネットを調べれば出てくるので、概要はすぐにお分かりになると思います。
「関係の質」とは、ダニエル・キムという学者が提唱している概念で、アメリカで従来の人事評価制度や成果主義を見直すものとして広がってきたものです。
アドビシステムやGE(ゼネラルエレクトリック)、マイクロソフト、GAPなどといった先進企業で導入し始められているものです。これは何かと一言で言うと、
社内の人間関係の質を向上させることこそが、成果や生産性を高める、という概念で、今までように「成果」にだけ基づいて評価を行うこととは、まったく別の視点がここにあります。
でも、考えてみるとこれって、日本では昔からごく当たり前のことではありませんか?
日本企業があまりにもアメリカの文化の影響を受けすぎているせいか、アメリカから入ってくるものにいままで振り回されていて、今度の最先端はなんのことはない、「もともと日本では当たり前のものだった」ものが、最先端ということで日本に入ってきた、そんな感じがしています。
まあ、今までの経緯は横に置きましょう。
この「関係の質」を高めるということは実は、皆さんもお分かりのように生産性向上に、そしてうつ、メンタル不調予防、解決にも非常に効果を発揮します。
ただ、米国人とは日本人では大きくパーソナリティが違うため、関係の質を高めると気に重要なコミュニケーションは、異なります。簡単に言うと、
・米国人の上司には、質問力が大事。米国人は率直に言うことにあまり恐れがないため、上司が質問すれば部下は答えます。つまり、関係の質を高めるには、上司の質問する力を高めればよいということになります。コーチングですね。
・日本人の場合は、上司が質問しても部下は本音は答えません。よって、日本人が関係の質を高めるには、上司には「察するコミュニケーション力」が重要なのです。
上司に察する力を高めるには何をすればよいと思いますか? 一番重要なのは、上司が自分自身の慢性的なストレスをコントロールできるスキルを身に着けてあげることなのです。
なぜなら、察する力とは利他力を意味しますのが、利他力が低いとは自分がストレスでいっぱいになっている時で、そんな時は部下の気持ちを察することは基本的にしんどくてできなくなるからです。
部下の目線で言うと、上司との関係の質を高めるとは、やはり自分自身のストレスをコントロールするスキルを身に着けることが必須となります。なぜなら、上司と深くコミュニケーションをするとは自分自身の不安や恐れを乗り越えるスキルがないとできないからです。
おそれが強いままでは、上司の深い話ができず、そうすると関係性はかわりませんよね。
で、上司と部下の関係性が変わると、生産性が向上しますね。そして、うつ、メンタル不調になる人とは、上司に対して恐れが強いため、率直なコミュニケーションをするスキルがない人なのです。
社員がどんなパーソナリティをしているのか。筑波大学名誉教授でストレス学者である、宗像恒次博士が開発した独自の行動特性判定テストで調べませんか?
生産性向上も、うつ、メンタル予防も、社員の性格=行動特性を調べ、社員の性格に合わせて関係の質を高め、幸福度を向上させることが、本当の解決策を生むと弊社では考えているのです。
御社でも社員の幸福度を高めることで、社員の働き甲斐を高める教育を導入していきませんか?
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2018/11/20
 前へ
前へ- 次へ
2018/11/25
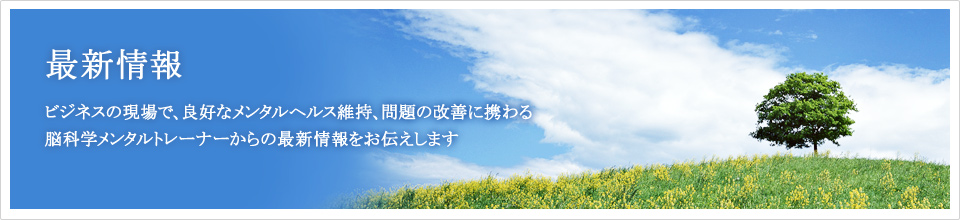
 前へ
前へ