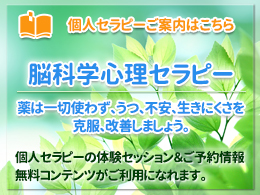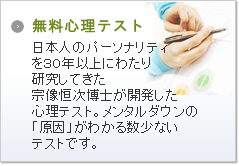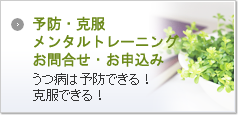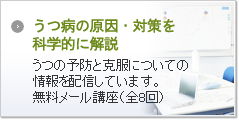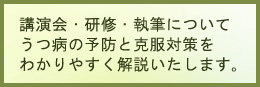企業メンタルヘルスご担当者向け情報 「脳科学メンタルトレーニングを組み入れると、メンタルヘルスの改善状況が見えてくる
よく企業に行ってメンタルヘルスご担当者のお話を伺っていると、こんな話が出てきます。それは、「お医者さんのアドバイスを聞いても、復職の時期って、よくわからないんですよね」ということです。
このご担当者様とのお打ち合わせの前に、休職されていたある方を面談していたのですが、その方のお話を伺っていると、その方もこんなことを言っていました。
「復職の時期を質問したら、もうすこし様子を見ましょうか、ということなんです。なんかあいまいで・・・」と。
私は、お医者さんが悪いというお話をしているのではなくて、企業側がお医者さんと我々、脳科学メンタルトレーニングの使い方がわかれば解決する問題だなと思いました。
というのはこういうことです。私たちは、3歳までの感受性を決めている脳内にある「扁桃体(へんとうたい)」の興奮を鎮めると、うつをはじめとするメンタルヘルス不調は解決する、と考えています。
実際、約15時間程度で大幅に改善する成功例をたくさん出しています。扁桃体の興奮の度合いを測定する診断テストは、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が開発しておりますが、我々の脳科学メンタルトレーニングを受けると、この診断テストの得点が劇的に変化するのです。
すると、扁桃体が沈静化したことが「数値で可視化」されますし、なにより本人の気持ちが非常に落ちつき、夜も寝られるようになり、気持ちも前向きになってきます。
脳科学メンタルトレーニングを行ってから、お医者さんに見ていただければよいと思います。そうすると、お医者さんは様子が良い方向に変化していることがわかると思います。
そうすると、「あと〇週間くらいで大丈夫そうだな」などと、的確な判断を下せると思うのです。お医者さんは、症状を改善する心理療法を行う人ではありませんので、お医者さんだけの治療を行っていると、非常にあいまいな症状判定になってしまうのです。
お医者さんが悪いのではなく、お医者さんもメンタルヘルス分野の一専門家であって、すべてをカバーしている人ではないということを、企業は知ることが大切なのではないかと思います。
企業は、それぞれの専門家の「使い方・役割分担」がわかればよいのです。お医者さんだけにすべてをお任せにしてしまうと、なんだかよくわからない症状判定の状況に陥ることがあると思います。彼らも困るのではないかと思うのですね。
やはり人事部が主導権を取って、各専門家を組み合わせて進めていくということが大事だと思います。
コラボレーションがうまくいくと、弊社が担当した某上場企業のように、うつで休職した人の再発が3年半の間、0%という結果がでるのです。
カウンセラーは、どういう専門家でしょうか。彼らはお話を聞くというプロです。聞いてもらえると、気持ちが楽になりますね。脳が記憶していることは、聞いてもらえると話すことができますね。ということは、彼らは、3歳以降に脳に保存されている記憶を引き出して、気持ちを楽にする専門家だということです。
顕在意識レベルの気持ちを整理整頓するお手伝いをするのだと思います。メンタルヘルス不調に陥っている方には、気力体力が消耗し自分の課題に向き合えない人がいます。そういう人々はお話を聞いてもらえると、すこしづつ元気が出てきます。
私はカウンセラーは、初期面談の役割にぴったりの方ではないかと思います。
しかし、冒頭で書きましたように、うつなどメンタルヘルス不調の原因は、3歳以下で完成する「扁桃体」の感受性にあります。これは筑波大学の研究であきらかにされています。
メンタルヘルス不調に陥る人は非常にデリケートな人が多いですが、このデリケートな感受性は、3歳までで完成するのです。
「3つ子の魂、百までも」ということわざが日本語にありますよね。まさにその通りなのです。つまり潜在意識、潜在記憶が問題で、それをあつかっているのが、我々脳科学メンタルトレーナーである、心理療法のプロが行っていることなのです。
こんなふうに各専門家の位置づけがわかり、使い方はまだまだよく知られていないため、なんとなく産業医だけを雇っていて、それでよくわからないとか、カウンセラーを社内に配置しているけど、なんとなく効果が見えないとか、そんな状況になっている企業が多いのではないかと感じます。
専門家を上手に使い分け、組み合わせて全員で対策にあたって行く。コラボレーションによって最大限の効果を引き出す、というやりかたをもっともっと知っていただけるよう、普及に努めたいと思います。
*脳科学メンタルトレーニングに関する資料をお送りします。こちらのお問合わせフォームからどうぞ。
2014/03/08
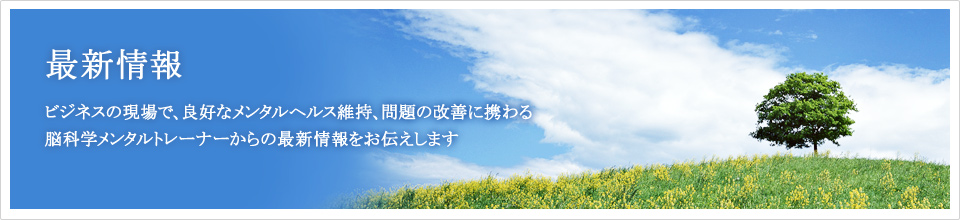
 前へ
前へ