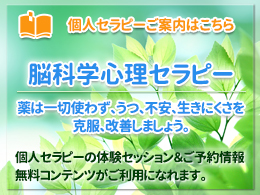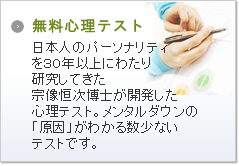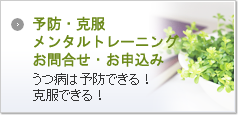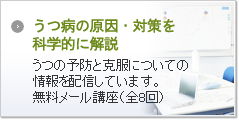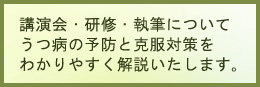企業メンタルヘルスご担当者向け情報 「うつの再発を防止するために脳科学メンタルトレーニングが目指すものとは」
脳科学メンタルトレーニングでは、どうすればうつやメンタルヘルス不調の再発を防げるかという方法論を持っています。こういうことを言うと、よく企業のメンタルヘルス担当者様にびっくりされるのですが、再発を防ぐには、以下のことが大切になります。
「自分の都合を言える人になること」
なぜこういうことが言えるかというと、それは筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が開発した、ストレス心理テストのデータの結果なのです。
たとえば1,2例を挙げると、「相手の顔色を気にして、自分の本音を抑える度合い」を見ている、自己抑制型行動特性尺(C.宗像恒次 20点満点)という心理テストは、日本人の平均点は約9点ということがわかっていますが、うつになる人は15点以上取ることがわかっています。
15点以上取るということは、まず、自分の気持ちを全く言いえないというレベルを表します。仕事では、負荷のかかることを求められるものですが、この心理テストの得点が15点以上取ると、だれにも何も相談できないということになるのです。
そして一人で悩み、ばたっと倒れます。
よく長時間労働がうつやメンタルヘルス不調の原因ではないかということで、長時間労働者に対して面談などを行っている企業は多いと思います。しかし、我々の研究では、メンタルヘルス不調に与える要因としては、長時間労働やパワハラなどの外部要因よりも、本音を言えない、という心理的内部要因のほうが影響がはるかに大きいということがわかっているのです。
もうひとつのストレス診断テストに「相手に察しを求める度合い」を見ている、対人依存型行動特性尺度(c.宗像恒次 15点満点)というものがあります。これは相手に「察しを求める」、つまり「言わなくても自分の心を読んでもらいたい」という欲求の強さを測定しているものです。
11点以上とると、うつになるリスクが非常に高い、ということがわかっているのです。察しを求める、とは、自分ははっきり言わないで相手に期待しているということです。昔の日本の組織であればともかく、今、察してくれる人はほとんどいないと思います。
この得点が高い人は、心が不安定になりやすく、先ほどと同じように仕事を一人で抱えたときに、だれにも相談できずにある日突然、ばたっと倒れることになるのです。
なぜ言えなくなるのでしょうか。
それは本人の脳内の感情の発電装置である、扁桃体(へんとうたい)が相手の「顔表情」に刺激を受けて慢性的に非常に興奮するので、意思決定の座である、前頭前野の血流量がダウンするからなのです。
要は、その人にとって苦手な人が職場にいるために、扁桃体の感受性が敏感な人は、その人に恐怖を感じすぎて、フリーズして何も言えなくなっているということです。
しかし、重要なのは「ある特定の人」に恐怖を感じるのではなくて、メンタルヘルス不調に陥る方の扁桃体には、一定の表情や声などに反応するパターンが潜在記憶として書き込まれているということです。
よって部署を変えればOKという問題ではないのですね。
最終的には、自分の都合をはっきり言えるようになれれば、うつやメンタルヘルス不調は再発しません。しかし、言えるようになるには、扁桃体の興奮を鎮静化する必要があります。
扁桃体は3歳で成熟する脳の部位なので、3歳以下の潜在意識に働きかけて、敏感すぎる感受性を鎮める心理療法が必要になるのです。それが脳科学メンタルトレーニングなのです。
お医者さん、カウンセラーなど、すでにいろいろ行っておられる方々と、脳科学メンタルトレーナーの我々が役割分担をして、チームを組むことで、某上場企業では3年半、うつで休職の方の再発率が0%という結果に貢献しているのです。
*脳科学メンタルトレーニングに関する資料をお送りします。こちらのお問合わせフォームからどうぞ。
2014/03/23
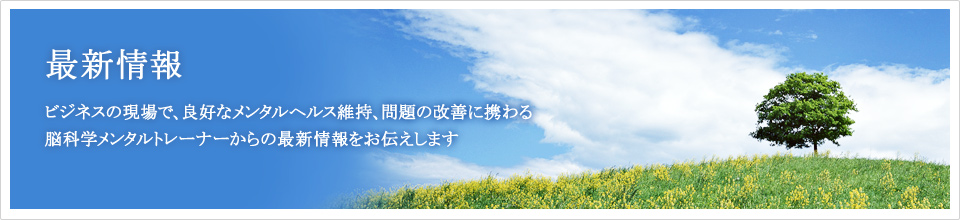
 前へ
前へ