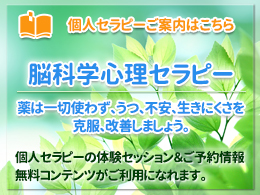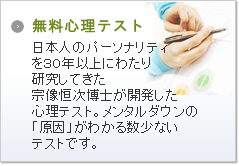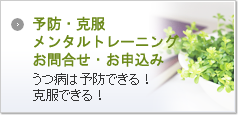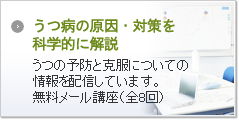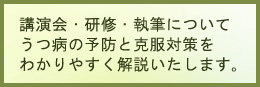企業メンタルヘルスご担当者向け情報 「脳科学メンタルトレーニングが提唱する、幸せを作り出す3つの技術がメンタルを予防する」
その人が幸せな気持ちになればメンタルヘルス不調は消える、というのは誰でもが直感的に理解していただけると思います。ところが、幸せってどうしたらなれるのだと思いますか?
脳科学メンタルトレーニングでは次のように考えており、これを満たすトレーニングメニューをメンタル予防対策メニューとしてプログラム化しています。。筑波大学名誉教授・宗像津べ次博士が、脳科学の視点から提唱しているテクニックです、
1.1日1回ドーパミンを放出させる小さなイベントを作る。
2.意味ある生き方をすること
3.扁桃体興奮を取ること。
1からご説明しましょう。ドーパミンとは、快感の感情と関連する脳内神経伝達物質ですが、よい予期ができる、と放出されます。つまり今晩おいしいものが食べられるな、と思うとうれしくなりますよね。うれしくなる=よい予期ができる、と、ドーパミンが出る、のです。
つまり、目先的によい予期ができない仕事ばかりしていると、気持ちが落ち込んできます。なので、職場では昔だったら飲みにつれて行ったりしましたよね。今では飲みは好かれないとしたら、たとえば言葉でほめるなど、すると、部下側に「この人といると、いいことあるな」という、よい予期を持たせることができると思います。
ここはアイデアですね。この会社にいると、いいことあるな、と予期させることです。
ストレスを瞬時にマネジメントできるテクニックを教える、なども一つです。こういうテクニックを身に着けていると、きつい時にも「なんとかなる」と、よい予期がもてますね。弊社では、メンタルテクニック研修を行っているのは、こういう考えがあるからです。
ほめ言葉でなくてもよいです。私が知っているある会社は、給料日に社長が社員一人一人に、感謝の言葉を書いた手紙を渡しています。これなどは、社員に、給料日が来ると社長に感謝されるという、よい予期を持たせることができる小さなイベントですね。大きい会社だからと言って何もできない、ということはないと思います。ここはアイデアですね。
2.仕事に、意味を見つけられるテクニックを身に着ける。
脳内の側坐核(そくざかく)という部位は、意欲や活力と関係します。意欲を出し続けるには、どうしたらいいでしょうか。率直に言うと、今やっている仕事に「自分がやる意味」を感じられるかどうか、ということです。
意味を感じられない仕事をさせ続けると、意欲が出ません。メンタルヘルス不調に陥るリスクが高まるでしょう。意味を感じるとは、会社が目指す方向が自分の目指す方向を一致している、という部分を見つけられることが一番です。
一般的に多くの会社では経営理念がありますが、単たるお題目のようになっていることも珍しくありません。ということは、そういう企業では、経営理念が誰の心にも共感を引き起こさないのです。これでは働く意味を感じさせることは難しいと思います。
実は、よくよく探していくと、組織の目標に対して自分自身の中に共感できる部分があることを見つけ出すことができるのですが、多くの人は日々の忙しさに紛れて、思考がマヒしたような毎日になってしまっているので、気が付かないだけなのです。
しかし気が付かないでいると、働く意味が見つけられませんから、意欲が出てこずメンタルヘルス不調に陥るリスクが高まるのですね。
仕事に意味を見つけるトレーニングは、メンタルヘルス予防研修として行うときもありますが、普通に「部下の働く意欲を引き出す」というテーマで、管理職向けにリーダーシップ研修として行ったり、入社3年目までの若手に研修として行ったりしています。
3.扁桃体興奮を止める。
目先うれしいことがあったり、働く意味を感じられても、それだけではメンタルヘルス不調を予防できるわけではありません。扁桃体の興奮を止めないとネガティブ感情が発生し続け、メンタルダウンするのです。扁桃体は、周りの人の「顔表情」激しく反応しますから、その人のとっての苦手な表情をした人に対する、感受性の課題を解決する=扁桃体興奮を鎮める、ということをすることが重要になります。
以上のように脳科学的には、3つの観点から予防対策を行うのが、もっともよい対策になります。しかし、現在広く行われている、メンタル予防研修とは、よくて上記のうちの一つを行っているか、または、上記のどれにも該当しないような、なんとなく「つかれたら、運動しましょうね」のような、科学的な根拠があるようなないような、ものがおおいかもしれません。
幸せを科学的に考え、そしてメンタルテクニックとして組織内に落とし込む。メンタル予防対策とは、新たな段階に来ているのではないかと思います。
メンタル予防対策にご興味ある方は以下のフォームから資料をお求めください。
2014/04/29
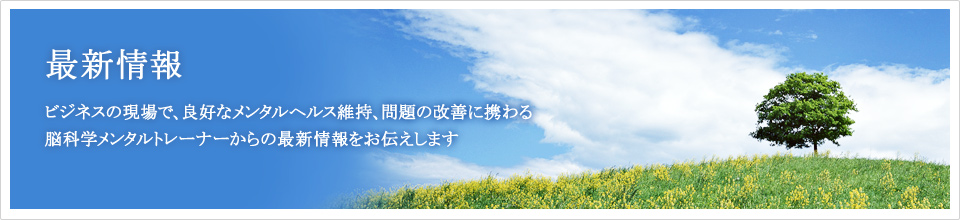
 前へ
前へ