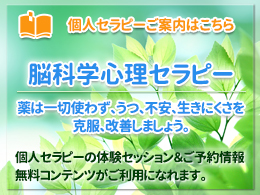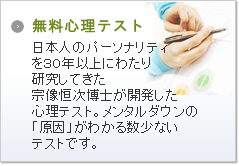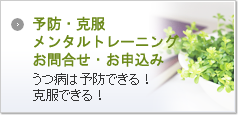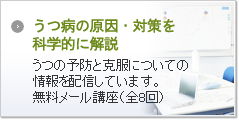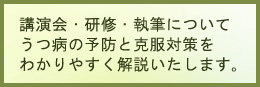企業メンタルヘルスご担当者向け情報 「うつを編呈する血液検査について、脳科学トレーニングが考える視点とは」
先日、日経産業新聞にこんな記事が載りました。
「うつ 血液で診断。社員に早期治療」 5/12 朝刊
血液中のエタノールアミンリン酸という数値によって、うつかどうかを判断する、というものです。そこで私も、脳科学メンタルセラピーの先生である、宗像博士に聞いたり、そのほかいろいろ調べてみました。結論は、こうです。
特許を出願した会社のプレスリリースによると、うつ病患者34名の人に対して使った結果、正しく判定できた確率は82%で、健常者31人に使った結果、うつ病でないと判定できた確率は95%なのだそうです。
私がこの記事から連想したことは次のことです。
1.まだいろいろ試行錯誤の途中なんだな、ということ。
2.うつエネルギーの持つプラスの面が見られなくなるのではないか、ということです。
まず1について。
まだ30名くらいの人数での実験なので、3000名くらいやったらどうなるのかな、と思ったのですね。正常の人を正常と判定するのは95%だとして、5パーセントは間違うわけで、3000名の5パーセントというと15人の人が「うつ」と間違って判定されるのです。
またうつの人をうつと判定するのは82%なので、3000名のうつの人にやると、540人の人がうつなのにうつではない、と出るわけです。
まだかなりリスクがあるな、という印象を受けました。信頼性の高い、心理テストなどとくみあわせることが大切なのではないかな、と感じました。
2について。
こちらのほうが私は強く思ったのですが、それはこういうことです。うつ、というと悪いものだと思う方が多いかもしれませんが、脳科学メンタルトレーニングでは、うつとは葛藤で苦しんでいる状態ではありますが、だからこそ現状を変えようという、強いエネルギーを内包している状態でもあるのです。
苦しい体験をして初めて人は自分が今までやってきたことを、真摯に振り返る存在でもあるわけで、その人が自分の成長課題に直面しているものでもあるのです。
なので、適切な心理トレーニング支援を行えば、その人はそれをきっかけとして成長することができるのです。
しかし、血液検査をして仮に「あなたはうつです」とわかったとしましょう。医療の世界の中で、うつは自己成長のチャンスであるととらえる発想はあるでしょうか。
たぶんないでしょう。なぜなら医療とは、薬を飲ませたりすることが医療だからです。
自己成長したら治る、ということになってしまうと医療は儲かりませんので、こういう発想には絶対ならないでしょう。
ということは、うつはすべて悪いもの、というとらえ方になるのではないかと思うのですね。
これは企業にとっては非常に大きな損失になるのではないかと思うのです。血液検査だけでは、そのひとのうつは成長しようとしているうつなのか、それとも成長意欲をすでになくしてしまっているうつなのか、または、動機づけによって成長意欲を引き出すことができるのかどうか、という点は見えないのです。
実は、脳科学メンタルトレーニングが持っているストレス診断テストは、このことがわかるようになっています。おなじうつでも、すでにあきらめてしまっているうつなのか、それとも成長しようと苦しみもがいているうつなのか。
もちろん人間ですから、完璧にあきらめている人はいません。動機づけによって、成長しよう! と思う人にもなれるのですね。
うつはわるいものではないのです。今まで、なぜうつになってしまうのかという原因が、わからなかったからこそ、いつのまにか悪いものになってしまったのだと思います。
うつは扁桃体の慢性的な興奮から作り出されます。
扁桃体興奮を鎮めることができると、今まで苦手だった人が苦手ではなくなります。そうすると、思ったように自分の意見が言えるようになります。
これは成長したということになりますね。
だからこそ、うつには成長の機会が眠っているわけです。
某上場企業では3年半、うつで休職した人の再発率0パーセントに貢献した脳科学メンタルトレーニングにご興味もっていただける方は以下のフォームから資料をお求めください。
2014/05/19
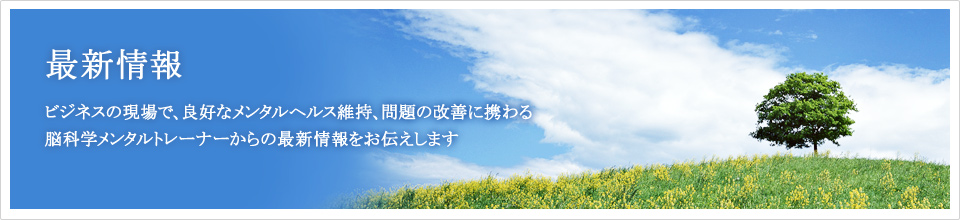
 前へ
前へ