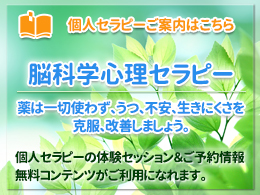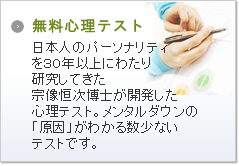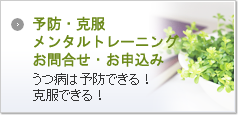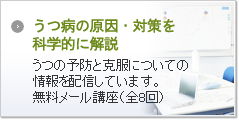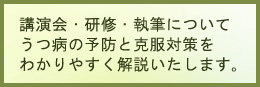企業メンタルヘルスご担当者向け情報「21世紀のメンタル対策に必要なもの。ストレス発生のメカニズムを科学に基づき、システマティックに解説する事 」
現在のメンタル対策の中で、一番大きな課題だと思うことは、ストレスというものをシステマティックに、しかも科学的な研究を背景を持って説明できるジャンルの人がいないということです。
これはメンタルヘルスご担当者の方でしたらよくご存じのことともいますが、さまざまな企業で行われているラインケアやセルフケアの研修の内容は、非常に通り一辺倒な一般教養的な内容のものが多いですよね。
またメンタル不調の方に「ストレスが原因ですね」とは言うかもしれませんが、ではストレスをどうやって解消したらいいかというと、「薬を飲んですこし会社を休みなさい」とか、「ゆっくり風呂に入りなさい」「運動しなさい」「ゆっくり散歩しなさい」というようなことは言うかもしれませんが、なかなかそれ以上の専門的なストレス対処法を、指導する専門職の人はいないのではないかと思います。
既存のメンタルの専門家といえども、ストレスについてシステマティックで科学的根拠に基づいた専門の教育を受けていないからです。
脳科学メンタルトレーニングの開発者である筑波大学名誉教授・宗像恒次博士は、ストレスというものを30年も前から、ストレスと脳、免疫、内分泌、自律神経、遺伝子発現、などとの関連性を研究している研究者ですが、弊社がよく企業でこういった知見に基づく研修を行うと驚かれるのです。
なぜかというと、こうした科学的な分野からストレスというものを説明するものを聴いたことがないという感想が一番ですが、なによりストレスとは、「可視化する事ができる」ということを初めて知るからだと思います。
心、というものは、実は「見える」ものなのですね。たとえば、不安緊張が高くなると、血液中のクロモグラニンAという物質や副腎皮質ホルモンの値が確実に上昇しますし、不安緊張が下がるとこれらの物質は低下するのです。
白血球の構成比率は、健康な人の場合、顆粒球(かりゅうきゅう)60パーセント、リンパ球35パーセント、マクロファージ5パーセント、という構成比率になっていますが、慢性ストレスが続くとこれらの構成比率が変化します。
たとえば、顆粒球70パーセント、リンパ球25パーセント、マクロファージ5パーセント、というように変化し、慢性ストレスが消えると元に戻るのですね。
私たち一般市民がこういうことを知っていると、健康診断で自分の血液のデータを見ると、自分で自分のストレスの状態がわかるのです。
これは新潟大学・阿保徹教授が発見した法則ですが、これをもとに私のセラピーの師匠である、筑波大学名誉教授・宗像恒次先生が、セラピーによるストレス軽減をしたクライアントの血液を調べた結果、確かにそうなることを確認しているのです。
「心」は見えるのです。全ての人の体の中で、心の変化は体に、正確な法則で影響を与えているのです。脳科学セラピーは科学をベースにしているからこそ、これらのことを知っているのですね。
ここがほかの心理療法との最大の違いと思います。で、いちいち血液を採取して判定するわけにいかないので、心の状態を簡易的に判定するために、独自の診断テストが作られているのです。
慢性ストレスはなせ起きるのか、と問われて、きちんと説明できる心理療法はあまりないと思いますが、脳科学セラピーの診断テストは、非常にはっきりと、ストレスが発生するメカニズムを説明することができます。
まず、慢性ストレスとは、よくうつの強さとして現れます。これが強くなると、苦しくなりますね。こちらの診断テストでは、50点以上取るとだいたいが夜が眠れなくなるレベルになってきます。
なぜよくうつが強くなるのかというと、不安な心理状態が強くなり不安が「持続する」からです。やはりこちらの診断テストで50点以上取ると、非常に不安が強くなります。
ではなぜ不安は強くなるのか。それはセルフイメージがよくないからです。セルフイメージとは、自分が自分に対して持っているイメージです。これは自己価値観という診断テストで判定できますが、10点満点中7点以下になると、自分に自信がなくなり不安が強くなってきます。
ではなぜ自信がなくなってくるのか。原因は3つあります。一つ目は、自己抑制という自分の本音の感情を抑え込む度合いが高いことから生まれます。自分の本音を言えないと、相手の顔色が気になってくるからです。こちらの診断テストでは11点以上取ると、だんだんメンタル不調が現れます。
二つ目は、対人依存が強くなること。これは相手に「察してほしい」という要求が強まることを意味しますが、対人依存が強くなると、相手はどうおもっているのかな、という気持ちが強くなり、不安が強くなるのです。9点以上取ると、心が非常に不安定になります。
3つ目は、情緒支援認知という、わかってくれる人がいると認知しているかという認知が低下すると、不安が高くなるのです。
ではこれらの3つの心理はなぜ悪化するのかというと、いろいろな要素があるのですが、すっ飛ばしてシンプルに言うと、実は、PTSSという心理が高いことが原因です。
PTSSとは、ポスト・トラウマティック・ストレス・シンドロームと言って、きずついた記憶群のことを意味します。
これは脳科学セラピーでは3歳以下の、イメージ記憶のことを意味します。扁桃体記憶のことですね。
扁桃体記憶が非常にネガティブだと、傷ついたという感受性が強く感じられるのです。扁桃体はイメージですから、音、におい、皮膚感覚、明暗、などに反応します。
大きな音が鳴ると、びくっと過剰に反応する人はいませんか? 狭いところに行くと、息苦しくなる人はいませんか? 暗い所に行くと、怖くなる人はいませんか? これらが扁桃体感覚で、うつやメンタルヘルス不調の方は、これらのイメージに非常に敏感に反応する人が多いのです。
扁桃体の感受性が敏感すぎると、相手の顔色をうかがう=自己抑制の点が高くなったり、察してほしい=対人依存の点が高くなったり、わかってもらえていないという認知が強くなったり=情緒支援の点が下がる、ということになり、その結果、そんな自分に自信がなくなり=自己価値観の点が下がり、不安が強くなり、それが持続すると、よくうつが高くなるのです。
こんなふうに心というものは、非常に規律正しく一定の法則で動いているのです。
今後のメンタルヘルスには、たとえばこんなふうに一定のシステムと科学的知見に基づく、説明をする必要があるのではないでしょうか。
メンタル改善状況を可視化できる、脳科学メンタルトレーニングトについて関心持っていただける方は、以下から資料をご請求ください。
2014/07/07
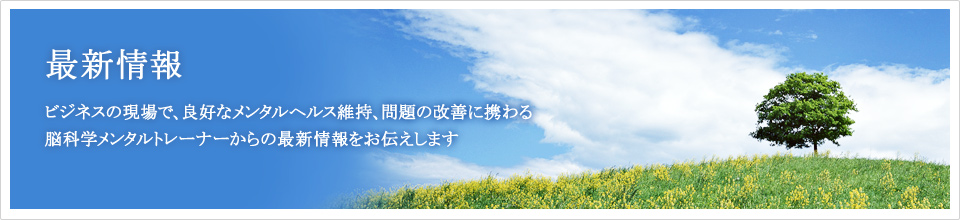
 前へ
前へ