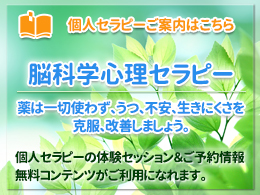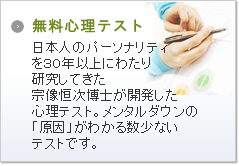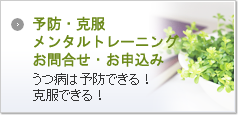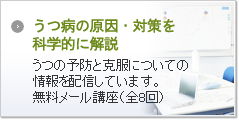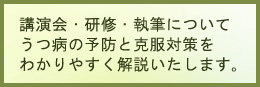企業メンタルヘルスご担当者様向け情報「セラピーとカウンセリングの使い方の区別を明確に行えると、うつやメンタル不調を解決できるメンタルトレーニングがわかる」
先日多くの企業のメンタルヘルスご担当者とお話していてきづいたことがありました。それは、カウンセリングと、セラピーの言葉の意味がごっちゃになっているということです。
カウンセリングとセラピーの意味が区別がついていないのは、多くの心理学ではっきりと定義がされていないことが大きいのではないかと思います。
カウンセリングという言葉は、化粧品にまで使われているくらいですから、訳が分からなくなりますよね。
脳科学メンタルトレーニングでは、カウンセリングとセラピーの定義を次のように明確に分けています。
カウンセリングとは、3歳以降の意識を扱うもの。そしてセラピーとは3歳以前の意識を扱うもの。これは弊社のアドバイザーである、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士の研究によるもので、脳科学的に調べると、メンタルヘルス不調には、脳内の感情の発電装置である、扁桃体(へんとうたい)の慢性的興奮が関係している、ということが明確にわかったころから来ています。
なぜなら扁桃体とは、筑波大学の研究では2歳8か月で成熟することがわかっていますが、fMRIを使った研究では、その人にとって怖い顔をしている人を見せると、扁桃体がものすごく興奮するということがわかっているからです。
うつやメンタルヘルス不調に陥る人は、必ず職場に苦手な表情をした人が存在します。新型うつの人は、職場に来るとうつになりますが、旅行にいくと元気ですよね。職場の中の誰かの「表情」に、扁桃体が反応しているのです。
3歳以下で成熟する、扁桃体が興奮しているのですね。
一方、私たちの3歳以降の記憶というものは、脳内の海馬(かいば)というところに貯蔵されています。海馬記憶とは、言葉による記憶です。3歳以降、私たちはしゃべれるようになるからですね。
で、この3歳以降の言葉による記憶を引出し、扱っているのは認知行動療法や傾聴を主体としたカウンセリングなのです。お話を聴くとか、原因を分析するといったことは、記憶にあることを扱ってるのですね。
しかし、問題は3歳までで成熟する扁桃体なのです。ここが激しく興奮しているのです。よって、3歳以前に作られた敏感すぎる感受性を良い方向に改善するという、ことをする必要があり、この手法をセラピーを呼んでいるのです。
しかし従来のセラピーと言うと、怪しげなものが多いというイメージがあるかもしれませんね。宇宙の癒しとか、水晶玉を使うとか、前世を扱うとか。
しかし私たちのセラピーとは、脳科学、免疫、内分泌、自律神経、など、慢性ストレスとこれらの生理的データの関連性を研究されて上で作られたものなので、最大の違いは、科学に基づいて作られているということです。
もう少しいうと、メンタル改善の状況が可視化できるということです。
セラピーもそうですが、多くのカウンセリングは、実施前後の効果を可視化できないものが多いのではないかと思いますが、それは科学をベースとしていないからだと思います。
多くの心理学やカウンセリングは、科学と言うよりも、文学的な世界から生まれてきているので、可視化という概念があまりないように思います。
以上のように、セラピーと、カウンセリングとでは、担当する分野が全く異なります。これが明確にわからないと、うちではカウンセリングやっています、と言いながら、セラピーはやっていなかったりします。
つまり真に効果的な心理療法はしていないということになります。
これではもったいないですね。
従来の精神医学やカウンセリングは、科学的な研究があまりなされていない分野ですので、なんだかよくわからないということが多すぎるのではないかと思います。
今後は、科学に立脚したセラピーというものが、従来のメンタル対策の中であらたなチームの一員として、既存の方々と連携していく時代になるのではないかと思っています。
某上場企業では3年半、うつで休職の方の再発0%という結果に貢献した脳科学メンタルトレーニングに関心持っていただける方は、以下から資料をご請求ください。
2014/09/21
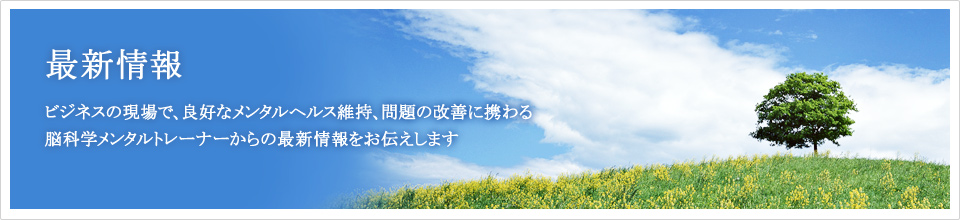
 前へ
前へ