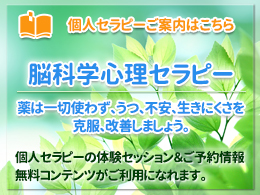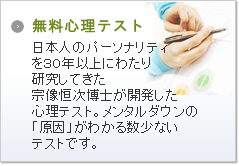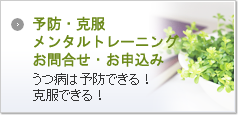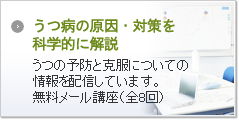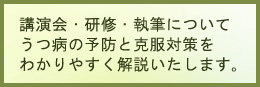企業メンタルヘルスご担当者向けメンタル情報「人が持つイメージの力によって、うつやメンタル不調は改善できる」
新年あけましておめでとうございます。弊社も1/6の夕方から営業を再開いたしました。
昨年は非常にたくさんの企業にお伺いし、ご縁をいただくことができました。今年もさらに活動範囲を広げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、昨年を振り返り今年を考えるにあたって、ひとつ目標にしたことがありますので、ここでご紹介させていただこうと思います。それは、
「イメージの力を広める」
ということです。
昨年末に、私はある方と知り合いました。この方は、主にプロスポーツ選手のメンタルコーチを行っている方で、プロ野球選手など、だれもがご存知の著名アスリートのメンタルアドバイザーとして、活躍されている方です。
この方は先のソチオリンピックでも、某種目女子チームのメンタルコーチとして、ソチオリンピックに行った方です。
この方がやっておられることは、もちろんプロアスリート相手ですから、結果を出すためのメンタルトレーニングです。つまり、イメージを活用したトレーニングなのですね。
プロアスリート相手のメンタルトレーニングというのは、最近かなりメジャーになってきたので、ご存知の方も多いかと思います。
この方といろいろお話をしてわかったのですが、イメージの力を最大限に活用して指導を行ってるのですね。
勝利している自分のイメージをありありと描くとか、これは様々なイメージワークのごく一部ですが、人の持ってるイメージの力というものを最大限活用しているのです。
ヒトが持っているイメージの力というものは、ものすごいものがあります。
これは何となくご理解いただけるのではないでしょうか。
さて、このお話を伺っていて私が思ったことは次のようなことです。それは、「勝つためにイメージの力の重要性はだんだん理解されてきている。実は、メンタルヘルスの分野でも、イメージの力によって、うつやメンタルへ流布不調を、そうとう回復させることができるのですが、まだまだこのことは知れ渡っていない」ということです。
スポーツでも、メンタル不調でも、究極的にはやろうとしていることは実は同じです。それは、望む自分になるために、その人のイメージの力を最大限活用する、ということなのです。
スポーツ選手でしたら勝つ自分になることが目標でしょうし、うつやメンタル不調の方でしたら、たとえばそこから脱却していきいきと働ける自分になる、ということになるのではないでしょうか。
メンタル不調の世界でイメージの力というものが、まだまだ全然認知されていないのはなぜかというと、私が思うにはメンタル不調は薬で治すもの、という思い込みが関係者に非常に強いこととか、お話を聞く、というカウンセリングが昔から使われていて、それ以外の手法がなかなか知られていないことなどがあるのかもしれません。
スポーツの世界も、かつては根性論だけが幅を利かせていました。根性は確かに重要ですが、それだけではだめだというのは、だんだん知れ渡ってきていますよね。
メンタルの世界も、薬や従来型のカウンセリングだけでは、だめなんじゃないかと考える人がだんだん増えて来ているのではないかと思います。
スポーツに使われるイメージの力が科学的に証明されていったように、メンタルヘルスに使われる、人が持つイメージの力を科学的に研究しているのが、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士によって開発された脳科学メンタルトレーニングです。
もちろん本人の意欲が基本的には重要ですから、あまりにも疲労困憊していて、それどころではないという人はお医者さんに行って薬を飲んで休息を取ったほうがよいでしょう。
しかし、のぞむ自分になるために、イメージの力を十分に使うということは、ものすごい回復や変化をご本人にもたらすものなのです。あきらめなければ改善ができるのです。
今年は、このことを科学的な根拠とともに広く知らせていきたいな、と思います。
某上場企業では3年半、うつで休職の方の再発予防0%という結果に貢献した脳科学メンタルセラピーに関心持っていただける方は、以下から資料をご請求ください。セルフケア法をきっちりやっていただければ、この上場企業のような結果をあなたの会社で出すことは、十分可能です。
2015/01/05
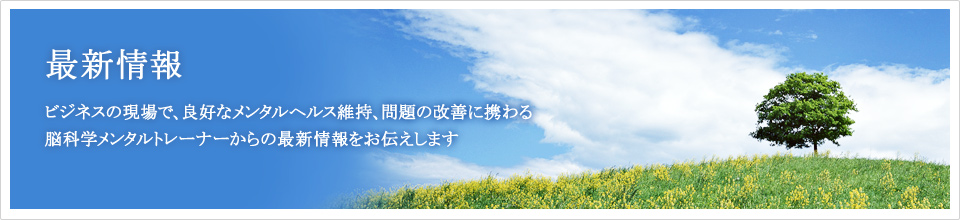
 前へ
前へ