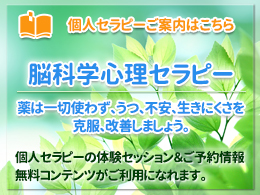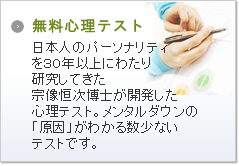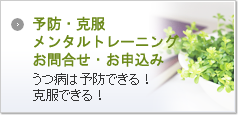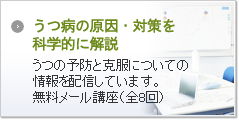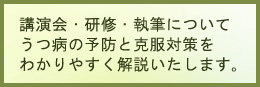企業メンタルご担当者様向け「”感じ方”の認知(扁桃体興奮)を変えると、うつやメンタル不調は改善する」
脳科学メンタルトレーニングでは、私たちの「感受性認知」を変える、ということによって、うつやメンタル不調を予防する、早期に回復させる、ということを行っています。
よく認知行動療法と何が違うの? と言われることがあるのですが、私たちも過去に現在よくある認知行動療法をやっていたのですが、次の点で全く違うと考えています。
「よくある認知行動療法とは、”考え方の認知”を分析させるもの。私たちが行っている脳科学メンタルトレーニングとは、”感じ方の認知”を変えることで、考え方の認知、と行動を変えるもの」
私たちも以前行っていた認知行動療法とは、自分が持っている「考え方の認知のクセ」を、本人に考えさせるのが特徴です。なので、紙に書かせたり、課題を出して考えさせようとします。
これが役立つ方ももちろんいます。
しかし、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士による研究で、脳の機能を詳しく調べていくうちに、どうやらうつやメンタル不調とは、脳内の感情の発電装置である、扁桃体(へんとうたい)の慢性的な興奮を深くかかわっている、と言うことがわかってきました。
扁桃体とは、0歳から3歳で完成する組織です。3歳以下のことは私たちはほとんど覚えていませんよね。このことを知った時に、従来の認知行動療法では、限界があるな、と言うことを悟ったわけです。
いくら分析させても、本人にはたぶんわからないだろう、と。
また、2013年10月20に放映されたNHKスペシャル「病の起源 うつ病」で、うつの原因は扁桃体興奮が関係している、という研究をしている欧米の科学者達の様子が放映されたことや、その番組で、扁桃体は魚にもある、ということが放映されたことで、私は確信を持ちました。
なせなら、魚はご存知のように、何かの気配を感じるとぱっと逃げますが、これは「考えて」逃げているわけではないのです。本能ですよね。
魚も持っている扁桃体を私たち人間も持っているということは、非常に原始的な脳である扁桃体の感受性とは、考えて分析できるものではない、と言うことを意味しています。
扁桃体とは、「感じ方」を決めているのです。分析して考え方のクセを理解しても、こわいものはこわい、のです。
つまり、扁桃体の感受性を変えることで、感じ方を変えると、考え方は変わり、その結果、行動は変わる、と言うことができるということなのです。
私たちも、既存の認知行動療法をたくさん試してみた結果、感じ方の認知を変えるためには、扁桃体興奮を鎮めることをしないと難しい、と言う結論に達したのです。
よって、私たちが考える「認知」とは、感じ方の認知+考え方の認知、のことで、考え方の認知とは、感じ方の認知を変えることで初めて変えることができる、ということになるのですね。感じ方の認知を変えるには、扁桃体の慢性的な興奮を鎮めることによって可能になり、そのためのイメージワーク法が、脳科学メンタルトレーニングです。
この方法は、一般的にはほとんど知られていませんが、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」には、ヘルスカウンセラーと言う名称で紹介されていて、産業カウンセラーなどと同等に紹介されているのです。
一般にはしられていませんが、国は知っているのですね。
感じ方の認知を変えることが、うつや」メンタルへルス不調の方の人の認知を根本的に変えること。
この考え方によって、宗像博士は、この方法を「情動認知行動療法」という名称を付けているのです。
情動=感じ方、を変えることで、認知を変える、と言う意味です。
某上場企業では3年半、うつで休職の方の再発予防0%という結果に貢献した脳科学メンタルトレーニング、およびセルフケア法に関心持っていただける方は、以下から資料をご請求ください。既存のメンタル対策と組み合わせ、この上場企業のような結果をあなたの会社で出すことは、十分可能です。
2015/07/06
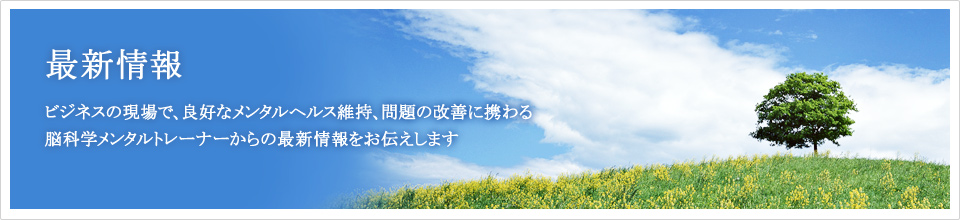
 前へ
前へ