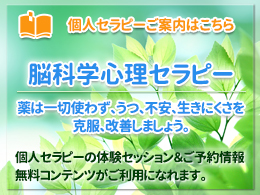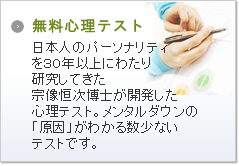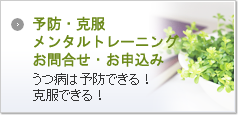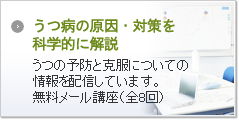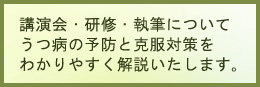企業メンタルご担当者様向け情報「ストレスとは、克服する技術を身に着けていれば、エネルギーや幸せの源になる、という考え方がメンタル対策を変える」
先日、電車に乗っていたら書籍のこんな広告を見ました。
「スタンフォードのストレスを力に変える教科書」 ケリー・マクゴ二カル 著
この著者は、アメリカ・スタンフォード大学の教授で、専門は健康心理学です。従来ある心理学とこの健康心理学の違いは、脳科学や免疫、内部分泌、自律神経、などの科学的な考察を背景に人間心理を研究している学問だということです。
弊社顧問である、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士は日本におけるこの先駆者ですが、米国でもこのような分野を研究する人が出てきたんだな、と思いました。
彼女の新しい本の表紙には、とても刺激的なコピーが印刷されています。
「不安、プレッシャー、過去のつらい経験はエネルギーの源。私たちはストレスを悪いものだと思っている。しかし、その思い込みこそが有害だとしたら? 困難を乗り越えて強くなる方法を解き明かしていく」
これを読むと、ストレスとは悪いものではないんだ、というメッセージを訴えているのがわかると思います。何が言いたいのかと言うと、
弊社が行っているヘルスカウンセリングと言う、厚労省のHP「こころの耳」にも推奨されている心理療法の考え方と非常に近いものがあるということです。
ヘルスカウンセリングは「こころの耳」のHPでは、「自己の成長課題を克服する支援を通して、メンタルヘルスを解決していくもの」と紹介されています。
つまりストレスを、自己成長のきっかけ、と捉えているところが似ているということですx。
私たちはこのような考え方を約20年前から発信してきましたが、やっとこのような本が出てきて、日本でもこうした考え方が広がっていくのではないかなと感じたわけです。彼女の前著である「スタンフォードの自分を変える教室」は、70万部のベストセラーになっていますから、今回の本もそこそこ認知されていくのではないかと思います。
ストレス科学をベースとしているヘルスカウンセリングでは、ストレスに対処するには大きく2つの対処法があると定義しています。
一つ目は、睡眠、休息、リラックス(散歩、入浴、気分転換、飲酒)などの、ストレス緩和法です。これらはたまったストレスを発散したり、緩和したりすると言う方法です。
これに対し2つ目は、そもそもそんなにストレスをためるようになった原因に向き合い、それを解決するという方法です。原因のほとんどはその人のパーソナリティ要因に原因があります。
その人が自分のストレスをためるに至った出来事に遭遇した時に、それを解決する方法論を自分の中に持っていないか、または、そのストレスに簡単に負けてしまうほどもともとセルフイメージが低い、と言う問題です。
前者を消極的対処法、後者を積極的対処法と呼びますが、現在行われているメンタルヘルス対策では、多くの場合、消極的対処法が行われていると思います。すこしストレスが強いとすると、医者に行って薬をもらうとか、休息するとか、と言うことが多いのではないでしょうか。
これらは大事です。しかし、これらはストレスは「悪いもの」と言う考え方から行われる対処法ではないかと思います。医療とは本来そういうものなので、これはある意味仕方がないと思います。
しかし、「ストレスとは対処法を知っていれば有益なものになりえる」という見方が、日本のメンタルヘルスの現場にほとんど存在しないことが、大きな課題ではないかと考えます。
つまり、ストレスとは克服できれば「あなた自身を成長させ、幸せにするもんなのですよ」と言う考え方が、ほとんどないように感じます。これはある程度、人生経験をした方であれば直感的にお分かりになることでしょう。
平たく言えば、こうなります。「ちょっとストレス強いからと言って、その都度医者に行くなどしていると、自分が成長したり幸せになるチャンスをみすみす逃していることにもなるんですよ」ということです。
今、ちょっとでもきついストレスに直面する出来事があるとすぐ、すぐにそれを避けるような風潮がありますが、それは両親や職場の先輩などから、それを克服する方法などを教わっていないことが大きいのではないかと思います。
もちろんストレス対処法がわからず長期間一人で苦しんでいた人は、免疫や内分泌の素点から見ると、ストレスホルモンや炎症性サイトカインと呼ばれる物質が脳に炎症を起こさせ、脳神経細胞を破壊する方向に進みますので、長期間こういう状態であることを放置すると、明らかに疾患が脳に表れ、その影響で不安定な精神状態になっていきます。
こうなると自分の課題に立ち向かう気力が持てないほど弱りますので、一定の医療措置は必要と思います。
しかし、今度義務化されるストレスチェックでは、高ストレス者と判定される人は、企業の中で5%から20%くらい存在すると言われています。
ストレスチェックそのものが病気発見のためのものではないと言ってみても、こんなに多くの高ストレス者にたいして、その人本人の課題を解決するやり方を教えなければ、企業はいったいどういうことになるのかなと私は考えます。
そのために職場改善をすると言うことだと思いますが、筑波大学大学院・博士課程の研究では、メンタルへルスの原因は環境要因よりも、本人のパーソナリティ要因のほうが圧倒的に因果関係が高いことが明らかになっております。
つまり、本人が課題を克服し、自己成長し、その結果幸せになる方法を教えることこそが、メンタル対策の重要な点ではないかな、と考えているのです。
ある調査によると、日本のビジネスマンは幸せを感じている人が海外のビジネスマンに比べて非常に少ないそうです。こういう調査が出ると私達は企業側の原因を考えますが、そのそも幸せは本人が作り出すものでもあります。
ストレスとは人生の色々な局面で必ずやってくるもの。それを克服する技術を知らなければ、ただ単につらい時期が続いていずれメンタルダウンするか、またはそこから逃げるだけか、最初から難しいことには挑戦しようとしない人が増えるか、またはストレスで元気のない人が増えるか、になってしまのではないでしょうか。
今の日本企業のビジネスマンの多くがこんな感じになっていると感じるのは、私だけでしょうか。
私達ヘルスカウンセリングやケリー・マクゴニガルが言うように、「不安、プレッシャー、過去につらい経験とはエネルギーの源」だ、克服する技術を知っていれば、幸せにさえなることがで切る、と言う考え方がこれから日本にも広まってくれば、メンタル対策も大きく変わるのではないかと思います。
現在、復職しても再発を繰り返す人が多いのは、ストレスに対する対処法を身に着けないままに復職するからだと思います。これが身につけば復職成功率は大幅に向上すると思います。
ストレスチェック義務化はやらなければならないとしても、どうせやるなら義務化の範囲だけやればよいというだけでなく、直面したストレスを乗り越えていくような技術を教え、活力ある人材を育成していきませんか?
厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。個人カウンセリング、ラインケア、セルフケア教育、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。既存のメンタル対策と組み合わせ、再発0%の上場企業のような結果をあなたの会社で出すことは可能です。
2015/11/03
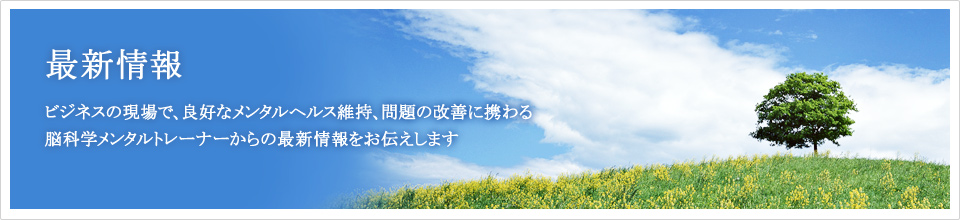
 前へ
前へ