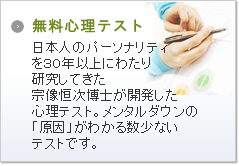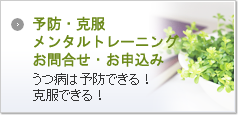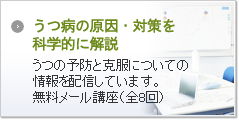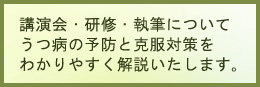企業メンタルご担当者様向け情報「感情は変えられない、という誤解と解けば、メンタルは解決する」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
先日、テレビを見ていたらこんなニュースが報道されていました。それは、
「某大学で、毛髪の分析することで、その人のストレスの強さと、それはいつごろかを分析できる」
というものです。私はこれを見て2つのことを連想しました。
一つ目は、
「だんだん客観的なストレス指標が出てくるのはよいことだな」ということです。
弊社顧問・筑波大学名誉教授、宗像恒次博士の研究は、もともとは生理データとストレスの関係について研究していました。
例えば、唾液中のコルチゾール値、白血球の構成比率、遺伝子発現、などとストレスの値は連動するので、私は、こういうデータを活用すれば一発でストレスの高低は明白なのに、なぜ、企業はこういう数値化を取り入れないのか不思議でたまりませんでした。
宗像博士の弟子(私も含め)たちの中には、医者、看護師、保健師、薬剤師、などが約1000人ほどいるため、こうした方々の協力を得て、血液などを採取して研究し、長年論文化されてきたのです。
しかし、一般企業で心理トレーニングを個人や集団に提供するときは、血液を採ったりはできないので、その代わりにその生理データと連動する、診断テストが開発され、弊社の診断テストはそういう研究によって作り出されているのです。
今回のようなニュースが注目されることによって、ストレスは生理データと関連するということが世の中でも注目されるようになってきた、良い流れだな、と思います。
さてもう1点の連想とは次のようなことです。
たぶん、毛髪を分析することで、ストレスが強い時期などを明白にすることはできるでしょう。しかし、そもそもストレスとはなにかという点がはっきりと理解されなければ、適切な対策はとれないだろうということです。
たぶん多くの場合、ストレスとは環境要因だ、という誤解がなされると対処はうまく行かないでしょう。それは、ストレスとは、残業が多いとか、人間関係が良くないとか、そういった外部要因で引き起こされるから、そちらを何とかしようとする方向に行くと思いますが、それではうなくいかないということです。
なぜなら、ストレスとはその人の「感じ方の認知」が作り出しているもので、内部要因が一番大きな原因だからです。このことは、筑波大学の博士論文で明白にされています。
今、義務化されているストレスチェックは、職場環境を何とかしましょう、という方向に対策が行われていますが、どの企業でもあまり効果的な対策が取れていないのは、明白です。
それは、内部要因について効果的な対策をとれていないからだと思います。
それはなぜか。1点あげるとすると、次のようになります。それは、
「感情は変えられない」と思っているからです。
現在、多くの企業で取りられている認知行動療法は、弊社は90年代から実施してきました。しかし、これではうまくいかないな、ということを早いうちから感じていました。
2000年を過ぎたころ、認知行動療法の日本の第一人者の方の研修を受けてその原因が明白になりました。それは、その博士がセミナーでこんなことを言っていたからです。
「感情を変えるのは難しいから、考え方を変えるという認知行動療法をやっている」
感情は変えられない、という前提に立っているのが、認知行動療法なのです。最近では、マインドフルネスなどと認知行動療法を合体させることで、感情に変化を起こそうとしているようですが、感情というのは脳内の扁桃体が大きな役割を果たしていますので、果たしてマインドフルネスが、どの程度扁桃体の安定に寄与しているのか、まだまだ未知数なところがあります。
扁桃体の過活動を鎮めることができると、感情は変化します。そしてこの実施前後の変化は、弊社の診断テストの数値によって、明白にすることができます。
いまあたらめて、メンタルを数値化して問題を明らかにし、実施前後の改善状況も数値化して報告できる、弊社のメンタルトレーニング法(個人トレーニング、集団トレーニング)を御社のソリューションとして取り入れていきませんか。
御社でも、本当の意味での教育的なメンタル対策に取り組んでいきませんか。そのやり方が、社員の幸福度を向上させるというやり方なのです。
ご興味あったらお問い合わせフォームから問い合わせをどうぞ。
また、健康経営、というフレーズも世の中に本当に定着してきました。弊社も2019年2月25日には、「中小企業のための健康経営」という切り口で、社員の幸福度実現セミナーを行います。詳細は以下。
このセミナーは、日本に健康経営という概念を根付かせた元祖である、健康経営研究会・副理事長の平野 治氏をお呼びして基調講演を行います。
健康経営は、医療が先導する病気直し型のもののイメージが先行していますが、本当の健康経営とは「社員幸せに働けるように支援すること」、つまり、Well-Being でいられるように支援すること、です。
こういった視点で具体的にはどういう施策を行ったらよいのかについて、2/25にセミナーを行いますので、ご興味があったらお越しください。
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2019/02/03
企業メンタルご担当者様向け情報「ストレスに対する誤解を解けば、メンタルは解決する」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
現在発売されている月刊雑誌でWedge2月号を読んでいたらこんな記事がありました。
「成果あがらメンタルヘルス対策 安易な”ストレス低減”から脱却を」
この記事の要旨は、ストレス低減を主たる目的とすると成果が上がらない。ストレスが悪いものではないという前提で正しい施策を行うことで、乗り切ることができる、というものです。
全く同感です。
この記事でも何度か書きましたが、現在企業で義務化されているストレスチェックは、ストレスとは悪いもの、という前提で実施されています。
だから高ストレス者とは悪い状態にある。よってストレスを軽減させましょう。医師面談をして、電話でカウンセリングを用意して、など。
で、結果として医師面談を受ける人はほとんどいないのです。
ストレスとは、本来、中立的なものなのです。扱いかたによっては、人と幸せにし、成長を感じさせるものであるし、自信をつけさせるものなのです。
たとえば、結婚を考えてみましょう。負担が増えますよね。子供が生まれたら責任が増える。ストレスです。だからと言って、結婚はやめましょう、などと言われたらどう思うでしょうか。
現在、医師をメンタル対策をの中心に置いている企業は多いと思いますが、医師はどうしてもストレスは悪いもの、という見方をします。
医療とはそういうものなのです。病気直しが医療の仕事なので。
彼らが悪いのではありません。企業の経営者やメンタル責任者が、医師に丸投げすることで、そうなってしまっているということなのです。
医療的な見方ではなく、マネジメント的な見方が大切なのです。マネジメント的な見方をすると、人材育成のためには、人に負荷の高い仕事をやらせるのは必要なことなのです。
高ストレスになるのです。問題は、それを乗り越えられるような指導をしていくこと。それが上司の役目なのです。
この記事でも何度か書きましたが、そういう意味で現在行われているストレスチェックは、高ストレス者をあぶりだしていますが、必ずしも高ストレスは悪いことではない、という視点が抜け落ちているのです。
高ストレス=悪いこと、になっていますよね。
なぜか。この制度を作ったのが厚労省であり、ストレスチェック制度を検討した委員会の構成メンバーのほとんどが医師や心理学の博士など、ストレス=悪いものと考える人々ばかりだったからではないかと思います。
こういったことを自発的に考える企業では、この制度のおかしさ、違和感を感じ取って、マネジメント的な視点でメンタル対策を行おうとしています。
つまり、ストレスを乗り越えられるよう指導することがリーダーシップであり、そのためのテクニックを身に着けるリーダー教育を行っているということです。
メンタル対策の本質とは、人材教育の問題なのです。もちろん、お医者さんは必要です。
でも、本質的なことをしっかり見ることができる企業は、教育の分野でメンタルをとらえているのです。
お医者さんに丸投げしている企業は、ストレス=悪いもの、と考えていますから、そうすると高ストレスの人にたいしてストレス低減をしましょう、となります。
仕事自体はストレスは生じるものですから、そうすると、矛盾が起きることになり、メンタル対策はいつまでたっても効果が出ないのです。
しかし、ストレスチェックも導入され3年たって、だんだんこういうおかしさに気づき始めている企業が増えています。良いことです。
御社でも、本当の意味での教育的なメンタル対策に取り組んでいきませんか。そのやり方が、社員の幸福度を向上させるというやり方なのです。
ご興味あったらお問い合わせフォームから問い合わせをどうぞ。
また、健康経営、というフレーズも世の中に本当に定着してきました。弊社も2019年2月25日には、「中小企業のための健康経営」という切り口で、社員の幸福度実現セミナーを行います。詳細は以下。
このセミナーは、日本に健康経営という概念を根付かせた元祖である、健康経営研究会・副理事長の平野 治氏をお呼びして基調講演を行います。
健康経営は、医療が先導する病気直し型のもののイメージが先行していますが、本当の健康経営とは「社員幸せに働けるように支援すること」、つまり、Well-Being でいられるように支援すること、です。
こういった視点で具体的にはどういう施策を行ったらよいのかについて、2/25にセミナーを行いますので、ご興味があったらお越しください。
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2019/01/15
2019/01/27
企業メンタルご担当者様向け情報「健康経営の本質がわかると、メンタルは解決できる」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
健康経営、というフレーズも世の中に本当に定着してきました。弊社も2019年2月25日には、「中小企業のための健康経営」というテーマで、セミナーを行います。詳細は以下。
このセミナーは、日本に健康経営という概念を根付かせた元祖である、健康経営研究会・副理事長の平野 治氏をお呼びして基調講演を行います。
健康経営は、医療が先導する病気直し型のもののイメージが先行していますが、本当の健康経営とは「社員幸せに働けるように支援すること」、つまり、Well-Being でいられるように支援すること、です。
こういった視点で具体的にはどういう施策を行ったらよいのかについて、2/25にセミナーを行いますので、ご興味があったらお越しください。
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2019/01/06
2019/01/23
企業メンタルご担当者様向け情報「従業員満足度と幸福度のの違いがわかれば、メンタルは解決する」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
幸福度向上のプラグラムについて経営者や人事のご責任者とお話していると、よく次のような質問を受けます。
「従業員満足度と幸福度というのはどう違うのですか? 従業員満足度調査はやっているのですが」
これは本当によく受ける質問です。実はこれに対して、幸福学研究の第一人者である、慶応大学教授・前野隆司博士はこのように述べています。
「従業員満足度とは、働く上での満足度を調べている。しかし、幸福度とはその人のプライベートを含めた満足度を調べるものである」と。
これを聞いてピンと来るでしょうか?
実は次のような意味です。
元来、仕事とはプライベートな要素も含むものです。たとえば、かつては昔の企業は、社内運動会をやったり、家族温泉旅行をやったりしていました。
プライべート的な楽しさも含めて、それが仕事の満足度、という意味だったのですね。よって、前野教授の研究では、プライベートの幸福度が高い人ほど、仕事への満足度、生産性が高い、ということなのです。
今では、仕事とプライベートを企業はきっちり分けて、業務に関する部分だけを切り離してやってきましたが、それが常行院満足度、という意味だということです。
もっと平たく言うと、こんなことをイメージしていただくとより分かりやすいでしょう。
プライベート的な人間関係も楽しい方がより、その会社にいることが幸せでモティベーションが上がると思いませんか? ということです。
従業員満足とは、その会社の給与体系や、福利厚生や、上司と部下の関係や、裁量権があるとかないとか、方針が明確だとか、残業が多いとか少ないとか、パワハラがないとか、業務に関しての満足度を見ているものです。
それに比べて幸福度とは、プライベートでも幸福度や満足度が高いかどうかを見る尺度で、より広範囲に、人生全般に満足度が高いかどうかを見ているもの、です。
人生全般に満足度が高い人の方が幸福で、その会社でメンタルが安定し、生産性やモティベーションが高いですよ、ということです。
そんな社員を育てたいと思いませんか?
そのためには、まずは幸福度尺度で御社社員の幸福度を測定しましょう。
ご興味あったらお問い合わせフォームから問い合わせをどうぞ。
また、健康経営、というフレーズも世の中に本当に定着してきました。弊社も2019年2月25日には、「中小企業のための健康経営」という切り口で、社員の幸福度実現セミナーを行います。詳細は以下。
このセミナーは、日本に健康経営という概念を根付かせた元祖である、健康経営研究会・副理事長の平野 治氏をお呼びして基調講演を行います。
健康経営は、医療が先導する病気直し型のもののイメージが先行していますが、本当の健康経営とは「社員幸せに働けるように支援すること」、つまり、Well-Being でいられるように支援すること、です。
こういった視点で具体的にはどういう施策を行ったらよいのかについて、2/25にセミナーを行いますので、ご興味があったらお越しください。
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2019/01/15
企業メンタルご担当者様向け情報「発達しょうがい解決のポイント(1)」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
あけましておめでとうございます。本日1/7(月)から弊社も新年お営業を開始いたしました。
新年のお知らせといたしまして、1/25の「キャリアの視点から考える、職場の発達しょうがいセミナー」をご案内します。私が講師を務めます。
ただし、お知らせした時点でもしかしたら60人定員に達しているかもしれません。なぜなら、昨年度9月にも実施いたしましたが、募集開始の3日で定員に達してしまったからです。
もし申し込めなかった場合には、私は本年の6月9日に日本産業カウンセラー協会の総会で、同じテーマで講演を行いますので、もしご都合つけばそちらにいらしていただければ幸いです。こちらはまだ、日本産業カウンセラー協会で、ご案内されていないと思います。
さて、昨年9月にも、この度と同じで、さんぎょうい株式会社とコラボして、発達しょうがいのセミナーを行いました。
その時に感じたのは、次のことです。
募集開始数日で満席になってしまうほど、ものすごく多くの企業の関心は高い。でも、多くの企業は、職場の発達障碍者を「邪魔者だ」と思っているということです。
なぜなら、その時の質問の多くが、次のようなものだからです。それは、
「職場でこんな人がいて、皆が困っている。なんとかうまい具合に、この人を退場させられませんか。」
もちろん、できることはあります。それは、私たちが行っている心理療法は今、VRを使ってある程度できるようにしているのですが、このVRシステム使って、彼らの感情を鎮めるということができるということが、筑波大学の研究で明らかになってきたからです。
彼らの感情を鎮静化するなり、改善するなりして、安定化すると、発達しょうがいは非常に職場に適応します。
発達しょうがいは、現在、脳の機能障害と認識されていますが、それが誤解で、弊社顧問・筑波大学名誉教授、宗像恒次博士の研究並びに、彼らへの心理療法の実践結果では、感情を安定化させると、職場への適応力が向上します。
それが数値でわかります。
弊社も自閉症スペクトラムやADHと診断された方の心理療法をたくさん行ってきましたが、彼らの持つ慢性ストレスを軽減してあげると、非常に職場に適応していくのです。
なぜなら、感情的におちついていくからです。
弊社の関連会社は現在、この我々が行っている心理療法をITやVRでできるように開発しており、この機器が様々な企業から引き合いがき始めております。
発達しょうがいを、脳の機能障害で変えられないと考えたら、もはや対策は薬か、無理やり適応させるためのソーシャルスキルトレーニング(社会適応化トレーニング)しかありません。
これをやらせるとものすごいストレスがかれらに起こり、とても大変なことになるでしょう。
実は彼らは、自分自身の個性を周りの誰にも理解されてこなかったせいで、ものすごい慢性的にストレスをためている状態なのです。このことを1/25のセミナーでお話しします。
では、どうしたらよいのか。
我々が開発している、ストレスを軽減するIT機器、またはVRを導入していきませんか、ということです。
ストレスとは、脳内の情動の発電装置である、扁桃体が過敏であることが大きな影響を与えており、扁桃体は職場のピリピリした雰囲気、表情、声のトーンに激しく反応します。このことは弊社顧問の研究で科学的に明らかですx。
よって、ピリピリした職場で発達しょうがいは、激しく問題を起こすのです。
扁桃体の過敏な感受性を、VRを使って改善していきませんか? このVR機器はすでに企業に導入されており、某企業の実証研究では、15人の管理職に2週間使用してもらった結果、行いストレス蓄積度が21%、ストレス敏感度は24%軽減したという科学的な結果が出ております。
発達しょうがいを固定化された機能障害、と考えてもよいですが、慢性ストレスを改善することで、仕事をさせやすい状態に持っていきませんか?
ご興味あったらお問い合わせフォームから問い合わせをどうぞ。
また、健康経営、というフレーズも世の中に本当に定着してきました。弊社も2019年2月25日には、「中小企業のための健康経営」というテーマで、セミナーを行います。詳細は以下。
このセミナーは、日本に健康経営という概念を根付かせた元祖である、健康経営研究会・副理事長の平野 治氏をお呼びして基調講演を行います。
健康経営は、医療が先導する病気直し型のもののイメージが先行していますが、本当の健康経営とは「社員幸せに働けるように支援すること」、つまり、Well-Being でいられるように支援すること、です。
こういった視点で具体的にはどういう施策を行ったらよいのかについて、2/25にセミナーを行いますので、ご興味があったらお越しください。
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2019/01/06
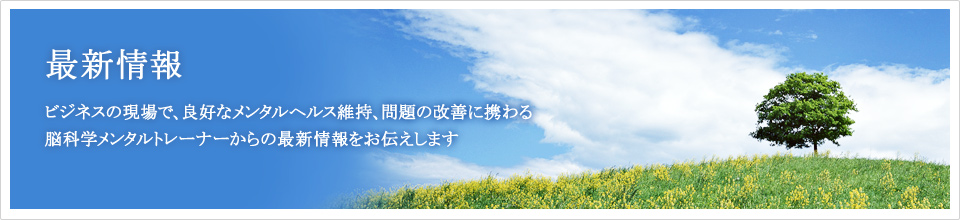
 前へ
前へ