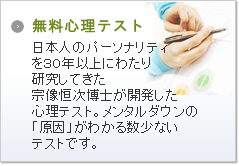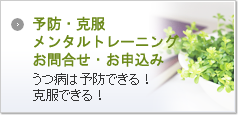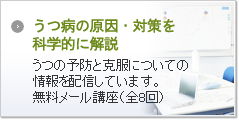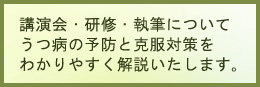企業メンタルご担当者様向け情報「感情労働に対する対策教育を行うと、従業員満足は向上し、うつ、メンタル対策も同時に行える。」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
仕事にはもともと「頭脳労働」と呼ばれるものと、「肉体労働」と呼ばれるものがありました。
しかし、最近はこれに加えてもう一つ、のジャンルがあると考えられています。それは、
「感情労働」と呼ばれるものです。
感情労働とは、感情を使わなければならない仕事という意味です。アメリカの社会学者である、A.
R.ホックシールドという学者がその著書で使い始めた言葉、と言われています。
一般的に感情労働が多い仕事とは、第3次産業、つまりサービス業なのですね。
たとえば、
・客室乗務員
・看護師や介護士
・コールセンターのオペレーター
などをイメージすると、なんとなく感情労働というものがわかりやすいのではないでしょうか。
たとえば、私の妻は看護師をしていますが、看護師とは一昔前は、ただたんに注射を打っていればよかったかもしれません。
しかし、私の妻の話を聴いていると、医師の診断や治療法に納得がいかない患者さんをなだめたり、
クレームを聴いたり、一方では横暴な医師やまた患者対応が下手な医師がいて、そういう医師たちを、なだめすかしながら気を使って診療をうまく回していく役目を負っているわけです。
「感情労働」ですよね。
弊社顧問でストレス学者・宗像恒次博士は、看護師の燃え尽きの研究をしていた時期があり、それ
によると、看護師は一般職の方々より燃え尽きる割合が高いということが報告されています。
しかし、今、私たち日本の仕事は多かれ少なかれ「感情労働化」していると言えます。
どの企業も、CS=Customer Satisfaction(顧客満足)には熱心に取り組むようになっているので、
今まで以上に、どの仕事も「顧客に気を使わなければならない仕事」になっているのです。
私の妻の病院は認知症の高齢者も相手にしているので、話を聞いていると、暴れだす高齢者をなだめ
たり、時にはたたかれたり、寂しいと訴える高齢者のお話を聞いたり、それこそ「感情労働」をやっているのです。
私の妻はこういう仕事は好きなようでメンタルダウンはしていませんが、介護の世界ではこんなふう
に気を使わなければならないことにものすごくストレスを感じる人がいるのではないかと、想像します。
対高齢者だけではなく、上司に対してもいろいろ気を使わなければならないとしたら、うつ、メンタ
ル不調が多発するのは無理もありませんね。
CS(顧客満足)を向上させたいのであれば、ES(従業員満足=Employee Satisfaction)を満たすことが必須です。これがないままにやろうとすると、社員は燃え尽きます。
パワハラが起きるでしょう。離職率も高くなるでしょう。うつ、メンタル不調も多発すると思います。
モティベーションも低下するでしょう。
しかしこう書くと、こんなご質問がわくかもしれません。
「全部が全部、会社の責任ではないのではありませんか? 本人の責任もあるのでは?」
もちろんその通りです。半分は本人の「ストレスに対する弱さ」に原因があります。
しかし、半分は会社に責任があると思いませんか?
なぜなら、CSをこの上なく高めて感情労働化して売り上げを上げたいのは、会社だからです。
そのための教育を会社が提供しないならば、社員はその会社を見捨てて他の会社を探すことになるでしょう。
離職の理由を社員は決して言いませんが、感情労働に対するしんどさが、離職の原因になっているのは、冷静に考えてみるとよくお分かりになるのではないかと思います。
社員の幸福度を高めるトレーニングによって、ストレスを自ら乗り越えるスキルを身に着けていただき、感情労働のストレスを仕事の喜びに変えていくトレーニングを御社でも導入しませんか?
御社でも社員の幸福度を高めることで、社員の働き甲斐を高める教育を導入していきませんか?
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2018/11/20
企業メンタルご担当者様向け情報「」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
御社でも社員の幸福度を高めることで、社員の働き甲斐を高める教育を導入していきませんか?
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
2018/11/19
企業メンタルご担当者様向け情報「社員の幸福を作るものがわかれば、離職低下、生産性向上、メンタル予防、改善が同時に達成できる」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
3年ほど前に私は、明海大学准教授・樋口倫子博士との共同プロジェクトで、「Well=Beingのための自己マスタリー促進支援」という研究・論文作成にかかわったことがあります。
これは、Well-Beingとは、「働きがい=幸せ」の意味で自己マスタリーとは、「自分の将来的になりたい目標と、現実の落差を見据えて積極的に学ぶ姿勢」のことです。
ということは、この研究は「働きがいや幸せに働くことを目指して、社員自らが積極的に学ぶ姿勢を強化するための方法論の研究」という意味になります。
皆さんは、社員が最終的に幸せだな、と感じるためには何が必要だと思いますか?
この研究から導き出されたものは、こうです。最終的に幸せだなと社員が感じるためには、キャリア上での成功体験の積み重ねが大事で、そのためには、「自己肯定感」と「問題解決度」の、この2つが能力向上が不可欠になります。
この二つがあって、粘り強く仕事に取組む姿勢が養われ、その結果、仕事上の成功体験が積み重ねられ、その延長線上に「幸福感」があるということです。
ですから、なんとなくスピリチュアルなことをやって、気持ちいいな~、幸せだな~、という気持ちになることが仕事上の幸福感、という意味ではないのです。
社員の幸福度が上昇すると、離職率低下、モティベーションアップ、パワハラ減、生産性向上、そして、うつ・メンタル不調の予防、改善、が同時に達成されます。これは感覚的にお分かりになると思います。
反対に、社員の幸福度が低い会社が、離職率は増加し、モティベーションが低く、パワハラが多発し、生産性は低下し、うつ・メンタル不調はいくら対策をとっても減らない、のです。
昨日、某IT会社で、「働きがいが向上する、幸福度向上プログラム」を開催し好評でした。
こういうテーマだと社員も集まるのですね。でも、メンタルセミナーをやります、メンタル対策をやります、だと社員は乗ってこないです。
社員が自発的に参加してこそ、メンタル対策は意味があると思いませんか? そして、メンタル対策とは幸福度や働き甲斐を向上させると、生産性向上と同時に解決するものだ、ということは研究上明らかなのです。
自己肯定感と問題解決力を同時に高めれば、達成されるのです。
弊社顧問・筑波大学名誉教授でWell=beingの研究者、宗像恒次博士と、その弟子で、明海大学准教授・樋口倫子博士、そして私も加わった共同研究プロジェクト、による、自己肯定感と問題解決力向上プログラム。
御社でも取り入れていきませんか?
御社でも社員の幸福度を高めることで、社員の働き甲斐を高める教育を導入していきませんか?
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
以上
2018/11/15
企業メンタルご担当者様向け情報「幸福度上昇対策とは、あるがままの自分を発揮すること。そのことでうつ、メンタルも自動的に改善する」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
企業において、うつ、メンタル不調をどう改善していくか、予防していくか、という点で大きな課題となるのは、ストレスチェック後の結果を企業を知ってはいけない、という点にあります。
企業は高ストレス者が誰なのか知ってはいけないので、どうにも対処が取れないのです。では、そもそもどうして 高ストレス者情報を知ってはいけないのだと思いますか?
いろいろな理由がるでしょうけれども、私はこう思います。そして多分、多くの方が納得していただけるのではないかと思います。
それは、高ストレス者は「病気」というイメージを多くの方が持ってしまっているからです。また、多くの場合、医師がストレスチェックの実施者であり、また面談希望者に対する面談は医師が行うとなると、どうしたってこのシステムでは、「高ストレス者=病気」と、だれもが思いますよね。
ということは、いくら会社側が呼びかけを行っても、面談を受ける人は非常に少ないでしょうし、メンタル対策をやります! と会社が意気込んでも社員はあまり乗ってこないでしょう。
つまり、現状のメンタル対策はネガティブなのですね。だから多くの人が乗ってこない。
医療とは、どうしてもネガティブなものなのです。病気を治すのが医療の仕事ですから。この機能は必要です。でも、企業が医療の対処法しか持っていないと、なかなかメンタル対策は進まないでしょう。
なにしろ社員がノってこないですから。
ではどうすればよいのか。それは、社員の幸福度を上昇させるという手法、対策をとることを弊社はお勧めします。弊社には個人的に申し込んでくる人はいいのです。そういう人は自腹でお金を払うし、ものすごい積極的です。だから16時間の集中メンタルトレーニングメニューを行うと、非常に改善する。
でも、会社に言われて申し込んでくる企業の高ストレス者は、そこまで自己改善のモティベーションが高くないのです。自腹でお金を払うわけでもないし。
そもそも、会社のおかげで高ストレスになっているという被害者意識も強い。ではどうしたらよいのか。先ほど書いたように、社員の幸福度を上昇させるというコンテンツ、プログラムを行うとよいのです。
幸福度を上昇させるとは、どういうことなのか。それは、弊社顧問でストレス学者、宗像恒次博士の研究では、それは、「あるがままの自分を発揮できるようにトレーニングしていく」ことで可能になるのです。
この記事を読んでおられる経営者、メンタル責任者のあなたにちょっと想像してみていただきたいのです。
あるがままの自分を発揮できている自分は楽しくないでしょうか? 幸せ度が上昇しませんか? そういう人はうつ、メンタル不調になると思いますか?
そして何よりもいいのは、
「あなたの生き方、働き方を今以上ハッピーなものにして、毎日を楽しく幸せに働くスキルを身に着けませんか?」
と言った方が、社員はノッてくるとおもいませんか?
そしてこれをやれば、自動的にメンタルの予防、改善になるのです。
御社でも社員の幸福度を高めることで、社員の働き甲斐を高める教育を導入していきませんか?
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
以上
2018/11/03
企業メンタルご担当者様向け情報「働き甲斐NO.1企業に見る社員特性を身に着ければ、社員の幸福度は上がり、メンタルは改善する」
★中小企業を応援する(株)オンリーストーリー様に取材していただき、WEBに弊社紹介記事を掲載していただきました。
★現在、9/2(土)にビジネス雑誌プレジデントのWEB版雑誌である、プレジデントオンラインに、私の記事「うつ、メンタル不調を解決する脳科学心理療法」の記事が4回シリーズで連載されています。
編集部から連絡があり、非常に多くの方に読まれているようです。興味あったら読んでみてください。
■4回目原稿(2017年9月25日(土))
■3回目掲載(2017年9月16日(土))
■2回目掲載(2017年9月9日(土))
■1回目掲載(2017年9月2日(土))
現在、専門家をはじめ多くの方々がうつ、メンタル不調は「寛かい」はできても解決できないと思っていると思いますが、きちんと解決できるのですよ、ということをビジネスマンたちに伝えたいなと思い、書きました。
<以下からブログ本文>
「働きがいのある会社」=Great Place To Work という調査機関があるのですが、ここは毎年世界60か国以上で従業員意識調査を行い、結果を毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しているところです。
日本でもこの調査は行われています。従業員数99人以下の規模の会社で2年連続1位のランキングになっているのがアクロクエストテクノロジー株式会社というIT会社です。
この会社はたまたま私とご縁があったため、どんな社員が働き甲斐を感じているのだろうと思い、弊社が持っている心理テストで調査をさせていただけないかとお願いし、実施させていただきました。
すると、やはり通常の会社とは全く異なる結果が出ました。大きくは2点あります。
1点目。「わかってくれる人が社内にいるか」=情緒支援認知の得点が高い。
情緒支援ネットワーク尺度というテストがあり、これは社内にわかってくれる人がいるかどうか、という認知を調べています。10点満点です。
2005年に弊社は、大手ビジネスマン6000人を対象に調査したところ、平均点は5.7点でした。つまり、わかってくれる人はいないという得点です。この心理テストは7点以上あると、わかってくれる人はいて、安心を感じるということになります。
アクロクエストテクノロジー社は、全社員の平均は、7.17点です。管理職に至っては7.45点です。
つまり、わかってくれる人がいる、と思っているのです。皆が安心感を感じています。ということは積極的に何でも言える人間関係ができているということです。
特筆すべきは、管理職の人々の上司に対する得点は、8.5点とものすごく高いのです。管理職の上とは経営層になりますので、管理職がものすごく経営層に対して安心感を感じている、ということになります。何でも言えるのです。
多くの企業はこの得点が低いので、部下は上司に対して決して本音は言いませんし、会議でも絶対本音は言いません。そして、上司の言われるがままに動くようになります。
上司はそのことに苛立ち、はっきり意見を言え、と言ったり、自分の頭で考えろ、と言ったり、挙句の果てはパワハラを引き起こしたりします。
働き甲斐は低いし、生産性は低下するし、うつ、メンタルが多発するのは目に見えるでしょう。
2点目。「周りの顔色をうかがい、本音を抑える」=自己抑制型行動特性尺度の点が低い。
この心理テストは、周りの顔色を気にする度合いを見ています。6000人のビジネスマン調査では、20点満点中平均点が9.8点です。つまり、かなり本音を抑え込んでいることがわかります。
この得点は11点以上取るとメンタルが不安定化します。平均点が9.8点ということは、相当の割合が11点以上取っていることが想定されます。
ということは、メンタルが不安定化している人々が相当いることがわかりますね。
アクロクエストテクノロジー社のこの心理テストの得点は、7.82点です。平均と比べるとかなり低いことがわかります。
ということは、「周りの顔色をあまり気にせず、何でも言える」というパーソナリティになっているということです。こうなると、会議では率直な意見交換がなされ、問題解決のスピードが速く生産性が高いことを意味します。
自分たちの意見が言えるので、社員たちの満足度が高いことはわかりますね。ストレスが溜まっても、周りの助けを言うことができる、ということも意味します。
うつ、メンタルもかなり予防できることがわかるでしょう。
結論として何が言いたいかというと、働き甲斐を高めることは、生産性向上、モティベーションアップ、離職率低下、社員定着率向上、パワハラ防止、うつ、メンタル不調の予防、に同時に効果を出すということです。
アクロクエストテクノロジー社に伺ったところでは、この会社には東大卒や東工大卒の優秀な人材が、大手企業の内定を断って入社してくるそうです。
また、離職率も極めて低く、伺った当時では5年間で辞めた人は一人だそうです。
いかがでしょう。
メンタル対策と言うと、医療主導の病気直し型の対策を行っている会社は多いと思います。それは必要でしょう。
しかし、働き甲斐を高める、という対策を導入すれば、うつ、メンタル予防も含め、一挙に様々な良いことが起こるのです。そして、働き甲斐を高めるとは、前述で述べたように心理テストの得点を改善すればよい、ということになります。
御社でも社員の現状を調べ、社員の働き甲斐を高める教育を導入していきませんか?
ご興味ある方はお問い合わせフォームからどうぞ。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
以上
2018/10/30
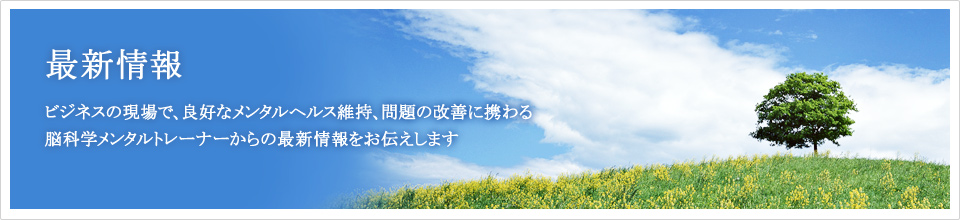
 前へ
前へ