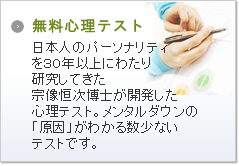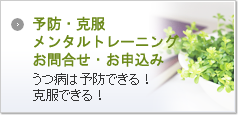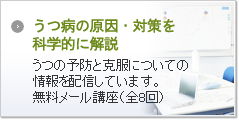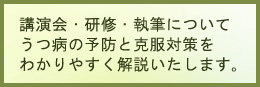企業メンタルご担当者様向け情報「健康観を変えよう。そうするとうつ、メンタル不調は解決する」
★6/25(日)13時~14時45分。「日本産業カウンセラー協会 神奈川支部総会」で山本潤一が講演します。テーマ→「脳科学心理療法のご紹介」。詳細は以下のHP。トップ部分の山本の写真のバナーをクリックすると申込みページに移動します(5/9からが申し込み受付だそうです)。
「日本産業カウンセラー協会 山本潤一講演申込みHPはこちら」
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
弊社顧問である、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士は1994年にロバート・ローゼンが書いた「ヘルシーカンパニー」という本を翻訳し、ヘルシーカンパニー、健康経営の概念を日本でいち早く提唱した学者です。
宗像博士が提唱する健康とは、「あるがままの自分自身の発揮して生き、働く」事を意味しており、これを私、山本は自己報酬型人生観、仕事観、と名付けております。
自己報酬とは、自分自身の内発的な喜びに導かれて生き働くことで、このような内発的な動機によって生き、働いている人は、そもそも身体的にも精神的にも病気になりにくいのです。
つまりうつやメンタル不調にもなりません。免疫も高く、これは宗像博士がかつて筑波大学大学院で指導していた、医師、看護師、保健師、薬剤師などの医療職にあった学生たちの研究論文からも疫学的に証明されています。
これとは逆に疲弊的ストレスを再生産する生き方、働き方を他者報酬に基づいた生き方、働き方のことで私、山本は「他者報酬型人生観、仕事観」と名付けています。
これは、「周りの顔色を気にし、自分自身の本音の感情を抑え自己犠牲して生き、働く」生き方、働き方のことです。これは長らく日本人にしみついた生き方、働き方で、こうしたあるがままの自分自身を発揮しない生き方、働き方が、うつ、メンタル不調を引き起こしや身体的病を作ることは、研究により明らかなのです。
ほとんどの日本人が今も、こういう生き方・働き方をしています。
昨今、「健康経営」が注目を集めていますが、主に健康診断を早く受診させるものが主流となっていると感じます。つまり、「病気がないことが健康」と言う考え方になっているのではないかと思います。
しかし、ヘルシーカンパニーの概念から行くと、病気がないことが健康なのではなく、自己報酬型の生き方、働き方をしているかどうか、つまり、あるがままの自分自身を発揮して生き、働いているかどうかが、健康だ、と言うことになるのです。
考えてみていただければわかると思います。
「周りの顔色を気にし、自分自身の本音の感情を抑え自己犠牲して生き、働く」生き方、働き方をしていると、常に自分は周りにどう思われているのか、上司に評価されているのか、などと言った不安や焦燥感、恐怖感、などに突き動かされている心理状態であり、評価されない出来事ことが起きると、うつ、メンタル不調になり、そして病気になっていくのです。
「周りの目を気にしすぎる」生き方・働き方=他者報酬型人生観、仕事観が、うつ、メンタル不調、病を作っていくのです。よって、病気が一時的に治ったとしても、この生き方・働き方を変えない限り、またいつか、うつ、メンタル不調、病気になるのです。
こういう考え方で行くと、病気があるない、が「健康」なのではないことがお分かりになるでしょう。健康的な生き方、働き方をしていることが「健康」なのです。
健康診断を行う事は大事ですが、それはあくまで「結果」を見ていることで、「健康」とは健康的な生き方をしているかどうか、という「プロセス」が問題だということです。そして健康的な生き方働き方とは、自己報酬型のことを言うのです。
うつ、メンタル不調とは、周りの目を気にしすぎる他者報酬型の生き方・働き方をしている人がなるもので、これを自己報酬型に変換させることができると、うつ、メンタル不調は解決していくのです。
また、本当の健康経営、ヘルシーカンパニーとは、社員のあるがままの個性を引き出して働かせているかどうか、自己報酬型の労働をさせているかどうかと言うことになるのです。
こういう考え方は、まだ既存の医療の中にはありません。よって、病気がないことが健康であり、病気なくすために健康診断をし、またうつ、メンタル不調を消すために薬を用いると言うことをするのです。
これは大事ですが、基本的に自己報酬型の生き方・働き方を変えない限り、うつ、メンタル不調、病、は再生産されます。多くの企業で、うつ、メンタル不調の再発が止まらないのはなぜか、はこうした理由なのです。
こういうことに経営者や人事担当者が目覚めることが重要なのです。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
この心理療法や、これを使った自己報酬型の支援。予防法、教育法、復職支援、などにご関心ある方は、以下のお問合せフォームから資料をお問い合わせください。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2017/04/22
企業メンタルご担当者様向け情報「高ストレスとは、あるがままの自分発揮の方法を模索している状態と言うとらえ方ができると、うつ、メンタル不調は解決する」
★6/25(日)13時~。「日本産業カウンセラー協会 神奈川支部総会」で山本潤一が講演します。テーマ→「脳科学心理療法のご紹介」。詳細決定次第、このHPでご案内します。
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
以前にも書いたかもしれませんが、昨年義務化されたストレスチェックの結果をいろいろな企業で聞いていると、自ら手を挙げて医師面談を受けた人は非常に少ないのがわかります。御社ではどうでしょうか。
弊社がお付き合いしている企業では、3000人の社員がいても医師面談を受けた人は0人です。誰も受けていなかった企業が少なくありません。
弊社のお付き合いしている企業で、800人規模の企業でで2人ほど医師面談を受けている企業がありましたが、この企業はもともと弊社がかなり懇切丁寧に社員に対して心理セラピーを行っていた企業であり、そういう企業の場合は、社員が企業のことをもともと信頼している面があるという特殊な要因があるためではないかと思います。
何が言いたいかと言うと、社員はストレスチェックを支持していないな、と直感的に感じるということです。3000人もいて医師面談に手を挙げる人が0人だなんて、このストレスチェックの制度自体がそもそも支持されていないことの表れではないでしょうか。
当初のEAP業界の予想では医師面談の希望者数は1パーセントですから、3000人なら30人くらいは出る予想でした。
高ストレス者のパーセンテージも、ずいぶんありえないくらい低いなと言う印象です。私は介護・福祉の企業のお付き合いが長いですが、介護・福祉の企業で高ストレス者比率が5パーセントというのは、ちょっと信じられません。
介護・福祉の企業はものすごい高ストレスがかかる仕事です。よくニュースで出てきますね。介護者が高齢者に暴力をふるって死なせてしまったなどという事件が。
つまり、社員がきちんと答えていない可能性があるのではないでしょうか。なぜか。社員はストレスチェック自体をあまり有益なものと考えていないせいなのではないかと私は感じます。
企業は、ストレスに対する考え方を改めるとよいのでではないかと思います。
このストレスチェックは、ストレス=病気=悪いもの、医師面談=あなたは病気だと診断される=周りから言われない不利益を受ける、と言う認識になってしまっているのではないかと思います。
これだと誰もが嫌ですね。
弊社の顧問であり、日本のストレス科学の草分けである、筑波大学名誉教授・宗像恒次博士の定義では、ストレスとは次のように考えています。
「あるがままの自分を発揮する方法を模索している状態」
つまり、ストレスとはあるがままの自分を発揮する方法がわからないときにおこるのです。
あるがままの自分を発揮することで、ストレスは消えるのです。ということは仕事でストレスがたまるとは、あるがままの自分を抑圧している状態であり、だからこそ職場はだんだん元気がなくなっていく。
根底には、仕事とは我慢するもの、滅私奉公するもの、苦しいもの、という日本人の古い労働観があると感じます。
ストレス科学では、ストレスとはあるがままの自分を発揮する方法を教えてくれているものと考えます。今はまだわからないからこそ、ストレスを感じている。ということは、あるがままの自分を発揮する方法がわかれば、ストレスは消えていくのです。
あるがままの自分を発揮すると、社員はものすごく元気になると思いませんか? これぞ働き方改革になると思いませんか?
そうです。
だからこそ、ストレスとは、幸せや健康に導くものだ、と弊社が言っている意味がお分かりでしょうか?
ストレスチェックで結果が出てあとは、社員自身のあるがままを発揮させる働き方を模索していきませんか? そのために、弊社顧問が開発している社員のあるがままの自分を診断する診断テストがあります。
ただ単に、病気だとか、うつだ、とか、だけを診断するのはもったいない。こうした医療的な対処法は大事です。しかし、もっと社員を幸せに健康に、生産性向上に導く方法があるのです。
一緒に働き方改革、社員をしあわせに導くことをやっていきませんか?
そういった取り組みにご興味あったら資料をご請求ください。ご説明します。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
この心理療法や、これを使った予防法、教育法、復職支援、などにご関心ある方は、以下のお問合せフォームから資料の医師などとのチーム連携に関心ある方は、お問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2017/04/17
企業メンタルご担当者様向け情報「問題解決スキルを身に着けさせるこそが、メンタルヘルス対策の本質的な対応策と位置付けると、うつ、メンタル対策は成功する」
★6/25(日)13時~。「日本産業カウンセラー協会 神奈川支部総会」で山本潤一が講演します。テーマ→「脳科学心理療法のご紹介」。詳細決定次第、このHPでご案内します。
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
うつやメンタル不調とは、そもそも「悩み」から生まれます。仕事の悩み、人間関係の悩み、など。
そして悩みとは必ずそこに「葛藤する感情」が存在するのです。もっと積極的に行動する自分でいたいが不安が強くできない、とか、上司に対してもっと深くコミュニケーションを取って自分の意見を伝えたいが怖くてできない、とか。
しかし、悩み自体は誰もが持つものですが、朝、布団から起き上がれなくなる人もいれば、そんなふうにはならずある一定に期間を経て元に戻れる人もいます。その違いは何だと思いますか? それは、一言でいうと、
「その人が悩みを解決する、問題解決スキルと持っているかどうか」
ということです。悩みを解決するスキルがあれば、そんなに深刻な状態にはならないのです。
この問題解決スキルとは、現在メンタルの世界でセルフケアと言われているものより、もっと積極的な意味を持つ対策法です。
多くの企業で行われているセルフケアとは、リラックスしましょうとか、スポーツしましょうとか、お風呂にゆっくり入りましょうとか、話を聴いてもらいましょうとか、そういうものが多いと思います。
これらのものは、緊張緩和やストレス解放などを行うもので、ストレスコーピングと言われるものですが、ストレス科学の私たちの考え方で行くと、先ほどの対処法は一時的なストレス緩和法で、問題解決をするものではないのです。
問題解決の方法は、問題解決型の心理療法を行っている私たちのようなセラピスト、カウンセラーが行っている方法の中にあります。
カウンセラーにも2種類いることをご存知でしょうか?
お話を聴く、などを主体とするカウンセラーで、これは緊張緩和、ストレス解放を目的とするもので、問題解決ではありません。
問題解決型のカウンセラー、セラピストとは、その方の感情的な葛藤が起きやすい性格的な原因に深く踏み込み、それを解決するということを行うのです。
もちろんカウンセラーや現行のメンタル専門家には、さまざまな役割の違いがありますので、経営者やメンタル担当者がその違いをしっかり理解して使い分けることが一番メンタル対策を成功させることになります。
そういうやり方を教え、自分自身でできるようにするのが、本格的なメンタル対策であり、それが本格的な問題解決型セルフケアだと弊社では考えております。
ストレス耐性が強い人とは、何があっても前向きな人なのではなく、問題解決力が高い人なのです。
そういう意味では、社員に問題解決スキルを教えることがまず重要で、なかなかうまく身に着けられない人は、メンタルダウンするリスクが高まりますが、そういう人は仕方がないので医療で対処していく、という使い分けをすることがもっとも効率が良いのではないかと弊社では考えます。
メンタル対策を医療に丸投げしている企業は、たぶん、ストレスが起きると医療ではすぐに「病人」として扱うでしょうから、社員に問題解決力が身につかず、それゆえ次から次へとメンタル不調者が出てくるでしょう。結局、人材の流出と費用の無駄がたくさん出るのではないでしょうか。
社員に問題解決力を身に着けさせることがメンタルを予防する強力な対処法なのだ、と視点を変えることが、今まで以上にメンタル対策を成功させると思います。
ご興味ある方は資料をお問い合わせください。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
この心理療法や、これを使った予防法、教育法、復職支援、などにご関心ある方は、以下のお問合せフォームから資料の医師などとのチーム連携に関心ある方は、お問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2017/04/11
企業メンタルご担当者様向け情報「うつ、メンタル不調者を採用しないような対策は取れるのだろうか」
★6/25(日)13時~。「日本産業カウンセラー協会 神奈川支部総会」で山本潤一が講演します。テーマ→「脳科学心理療法のご紹介」。詳細決定次第、このHPでご案内します。
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
いろいろな企業を訪問していると、よく
「うつ、メンタルリスクの高い人は採用したくないのだが、それを見抜く方法はあるか?」と相談されることがあります。
結論から言いますと、それはできます。なぜかというと、政府が義務化しているストレスチェックは、うつ、メンタル不調に影響を及ぼす外部要因(環境要因)を診断しているのですが、弊社顧問が開発している診断テストは、うつ、メンタル不調に陥る本人の内部要因(内部リスク)を判定するものなので、本人のリスクがわかるからです。
うつ、メンタル不調は、現在の多くの専門家は原因をわからないとしている方が多くいますが、弊社顧問の研究では、「ある性格傾向の高い人がなる」ということがはっきりしているからです。
ですので、その性格傾向を正確に測定すればわかるからです。
しかし、です。御社がそういううつ、メンタル不調リスクを測定する診断テストを行っているということが世間に知れ渡るようになると、御社はたぶん評判を下げることになるでしょう。
だからそういうネガティブな判定のために使わない方がよいと私は思います。代わりに弊社がおすすめする方法があります。
それは、御社の業務上、必要とされるコミュニケーションレベルを明確に定義して、それに見合う人を採用するための職業能力を測定するということです。
弊社には弊社顧問が開発した、「行動特性尺度」というものがあります。たとえば、御社にはどんな行動特性の人材がマッチしているとお考えですか?
御社に企業特性に合う、行動特性の人材を測定するわけです。
うつ、メンタル不調者とは、基本的にその企業が求めている行動特性とは合わない人材が採用されている可能性が高いと、弊社では考えています。
つまり、求められる職業上の行動特性が合っていない、から発生するということです。
私はずいぶん昔、人材教育の会社に勤めていた時期がありましたのでわかるのですが、よく企業が行っている適性診断テストというのは、営業に向いているとか、経理に向いているとか、そういう職種に合っているとかいないとかかなり大雑把に診断するものが多く、それよりもその方のコミュニケーションのタイプを細かく調べる者のほうがよいのではないかと思っていました。
たとえば弊社の行動特性尺度には、しゃべり方のタイプがわかるものがあります。一例ですが、ムード重視の話し方をするタイプ、論理的な話し方をするタイプ、口での表現を遠慮するタイプ、など。
ムード重視タイプや論理的なタイプは管理職を求める企業には向いていますが、遠慮するタイプは管理職には向いていません。研究職に向いています。
また、論理的なタイプは介護や医療など人の世話をする仕事には向いている人が多くいますが、遠慮するタイプは人と接するよりは介護技術の研究や書類作成などに向いています。
またムード重視タイプは、人と接する業務には向いていますが、目立ちたがり屋なので、地味な仕事にはあまり向いていません。
というように、行動特性があるのです。
その人それぞれの行動の特性を生かしてこそ、業務効率アップであり、従業員満足向上です。そしてこれがメンタルリスク低減になるのです。
ご興味ある方はお問い合わせください。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
この心理療法や、これを使った予防法、教育法、復職支援、などにご関心ある方は、以下のお問合せフォームから資料の医師などとのチーム連携に関心ある方は、お問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2017/04/03
企業メンタルご担当者様向け情報「チームを構築できる経営者、メンタル担当者がいると、うつ、メンタル不調は解決できる」
★6/25(日)13時~。「日本産業カウンセラー協会 神奈川支部総会」で山本潤一が講演します。テーマ→「脳科学心理療法のご紹介」。詳細決定次第、このHPでご案内します。
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
先日、3/22に厚労省が以下のような発表をしました。3/22朝日新聞デジタルによると、
「睡眠薬や抗不安薬、抗てんかん薬として処方される「ベンゾジアゼピン(BZ)系」という薬などについて、規定量でも薬物依存に陥る恐れがあるので長期使用を避けることなどを明記するよう、厚生労働省は21日、日本製薬団体連合会などに対し、使用上の注意の改訂を指示し、医療関係者らに注意を呼びかけた。」
「対象はエチゾラムやアルプラゾラムなど44種類の薬。BZ系薬は短期の使用では高い効果を得られるが、薬をやめられない依存性や、やめたときに不安、不眠などの離脱症状が生じることがあるとされる。日本では広く使われているが、欧米では処方が控えられ、長期的な使用も制限されている。」
とのこと。
44種類を見ると、よく聞くデパスやソラナックス、アモバン、ワイパックスなど、ほとんどのものが入っています。
ポイントは、「規定量でも薬物依存に陥る可能性がある」また、「やめたときに、不安、不眠、などの離脱症状が生じることがあるとされる」とのこと。
不安や不眠を改善するために使用しているのに、やめる時に不安や不眠などの離脱症状が生じるときがあるとか、まるで冗談みたいな話です。
また、「承認用量の範囲内でも、薬物依存が生じる。漫然とした継続投与による長期使用を避けること」と厚労省は注意しています。
承認用量を守っていても薬物依存に陥る可能性があるとすれば、もうこれは、医師と言えどもどうやってコントロールするのでしょうか?
また、「漫然とした長期使用」というのは、どう定義できるのでしょうか?
こういう答えが見えない問題は、メンタルの問題に関係なく、今の時代あらゆる分野に生じます。こうした時に、経営者やメンタル担当者がリーダーシップをとって判断していく企業は、メンタル問題に対し最善のアプローチができるのではないかと思います。
自ら判断するのではなく、医師などに丸投げしていると、なにも見えないかもしれません。
弊社とお付き合いしている企業で非常にメンタル対策がうまくいってる企業では、医師、産業医、我々のような心理士、にチームを組ませ、担当者がリーダーシップをとって、運営している企業です。
つまり、それぞれはそれぞれの得意分野、不得意分野があり、それを担当者がよく把握して、チームを組んで全員で問題解決する対策を取ってるのです。
うまくいかない企業とは、医師に丸投げしてる企業です。今回の厚労省の発表を見ればわかるように、承認用量を守っていても、薬物依存になす可能性があるとしたら、よほどのベテラン医師でないとまずは、その見極めはできないのではないでしょうか。
職人技、プロのカンの世界だからです。メンタルに関し、そこまでのプロレベルに達している医師は、そんなに多くないと言えるのではないでしょうか。
医師次第となると、もし本人が薬物依存になったとき本人はその医師を選んだ会社を訴える可能性があります、その場合、会社は医師を訴えることになるでしょう。
医師は、受けて立つ自信があるでしょうか? ある医師は少ないでしょう。
となると、現実的にこの問題の対処法を考えたとき、そこまで薬物を使わない対処法を考えることが重要ではないかと私は思います。よってこの問題を自主的に考え、対処するには経営者、メンタル担当者のリーダーシップが重要になるのです。
先の企業のように、そこまで薬を使わないとしたら、心理士を含めたチームとして対処していくことが重要ではないかと思います。それぞれの専門家を使い分けるには、経営者、メンタル担当者のリーダーシップが必要になるのです。
医師に丸投げしていると、これはできないのではないでしょうか。
今回の厚労省の発表は、こういう流れを加速する事になえるのではないかと思います。
弊社は、日本で唯一、本人が無自覚な感受性を担っている脳内の情動発電装置である「扁桃体」にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを解決し、心理課題を生産性向上、働き方改革へ解決ていくサービスを提供している会社、です。
この心理療法や、これを使った予防法、教育法、復職支援、などにご関心ある方は、以下のお問合せフォームから資料の医師などとのチーム連携に関心ある方は、お問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2017/03/28
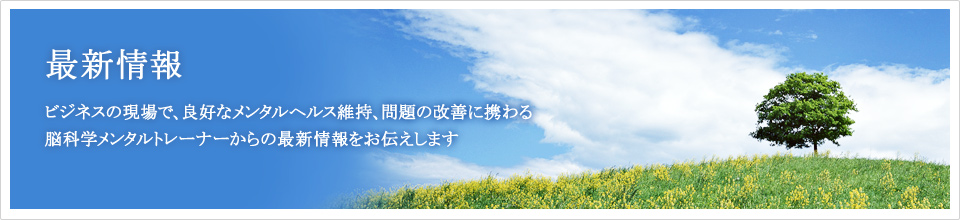
 前へ
前へ