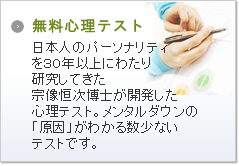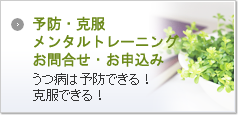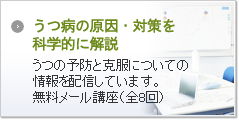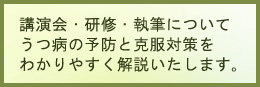企業メンタルご担当者様向け情報「ストレスとは、人を成長させるための与えられた課題だ、という視点が本当のセルフケア」
<お知らせ>
★20年のお付き合いがある超ベストセラー作家・本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を紹介してくださいました。ご興味あったら以下からお聞きいただけます。
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/16発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
先週、超ベストセラー作家で、私とは20年来のお付き合いがある、本田健さんが、彼が今やっているネットラジオ番組(ポッドキャスト)「Dear Ken」で、私の新刊本「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」を、番組内で紹介してくださいました。
正直言うと、うれしかったですね。
もともと約20年前からお付き合いがありましたが、さらに深くお付き合いするようになったのは、リーマンショックの余波で私がすべての仕事がなくなり、当時結婚したばかりの夫婦関係が最悪でボロボロだったときです。
彼には、夫婦ともどもさまざまなアドバイスをいただき、助けていただきました。本当に助かりました。
それと同時に、当時私自身は、うつ状態にありましたが、前から学んでいた心理療法を自分自身に行うことで、夜も眠れず、死にたい、という気持ちが起きていた状態から、ものの見事に復活できました。
本田健さんからのアドバイス、そして自分自身で行った本格的心理療法に基づくセルフケア。この2つで最悪期を乗り越え、その時の体験をまとめたものが、私の本、「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」です。
この経験を通して学んだことは、あの経験を通りぬけるための様々な経験をしたからこそ、今は夫婦関係は非常によくなりましたし、かつてのような環境変化で自分自身の仕事が影響を受けないように、今では慎重なビジネスモデルを構築しています。
何が言いたいかというと、私が経験したあのものすごいストレスとは、「私を成長させる糧」だったということです。そこでの課題を学び終えたときに、あのストレスは消え、うつ状態は消えたのです。
私は、本当のセルフケアとは、「その人の課題を学び終えること」だと考えます。ストレス科学の分野では、こういうストレス対処法を、積極的ストレス対処法と言い、「問題解決」することでストレスを乗り越える方法です。
一方、今多くの企業で実践されている、ストレスコーピングというものは、どちらかというと、お風呂に入りましょう、スポーツしましょう、睡眠とりましょう、など、今のストレスを「緩和」させようとするもので、ストレス科学の世界では、消極的ストレス対処法と呼ばれるものです。
ストレスコーピングは大事です。同時に、問題解決型のセルフケアを行うことが、本当の意味で再発を防止するものになると弊社では考えております。
なぜ、本当に意味での再発防止になるのか。それは、そこから「課題をしっかり学ぶ」からです。
そこで何かを失敗したから、そういう最悪の事態に陥ったのであり、それがなんだったかをしっかり学ぶからこそ、同じことを繰り返さないのです。
このストレスは「成長のための糧」だったのです。
人として一回り大きくなったからこそ、仕事の能力も高まるのです。企業としては、こういう人材になってほしいのではないでしょうか?
高ストレス者を病気だ、と扱い視点は、大事です。同時に、本当の意味のセルフケアとは、これを成長のための一つのきっかけと考え、その人の課題を学ばせる、ということなのです。
そして行っているのが、私たちプロ心理療法専門家なのです。
弊社は、日本で唯一(いや、世界で唯一かも)、企業向けに扁桃体にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の原因である、慢性ストレスを改善していく心理療法を提供している会社、です。
ご関心ある方は、以下のお問合せフォームからお問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/12/14
企業メンタルご担当者様向け情報「11/28発売のビジネス雑誌、プレジデントに、掲載されました」
<お知らせ>
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受け,11/28発売号に掲載されました。P34に「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」ということで、精神科医、脳生理学者、脳科学者などと一緒にのっています。もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/14発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
昨日、11・28に発売された、ビジネス雑誌「プレジデント」のP34に、「嫉妬・スマホ・睡眠の脳科学」という特集ページに、私がインタビューされた記事が掲載されました。
主に怒りのストレスをどうコントロールしたらよいのか、という内容で、私は自分が出版した新著「不安遺伝子を抑えて、心をす~っとラクにする本」の内容をもとに、不安遺伝子と脳、メンタルの関係につて解説しています。
私のほかに、精神科医、脳生理学者、脳科学者、が一緒に掲載されていますので、ご興味あったらご覧ください。
この特集の冒頭のページを見ていただければわかりますが、怒りの感情はなぜわくのかということについて、精神科医の方が、
「怒りに密接にかかわるのが、脳の中にある大脳辺縁系の中の扁桃体です」と
解説しています。
最近は、今年6月に放映されたNHKスペシャル「キラーストレス」でも、扁桃体のことが紹介されていましたが、うつ、メンタル不調の原因となる慢性ストレス感情を発生させるのは、扁桃体だということがかなり一般的に知られるようになってきました。
一般社員でも知っている人が増えてきていますので、各企業で行っているメンタル対策は、扁桃体を安定させるのにどのように役立つのか、ということをきちんと社員に説明できないと、社員から信頼を得られないようになってくるのではないでしょうか。
弊社に個人的に心理療法を受けにくる方の中には、大企業で現在休職している人とか、復帰したが安定しない人などがたくさん来ますが、多くの方が口をそろえて言うのは、「自社のメンタル対策、復職支援プログラムには、扁桃体に働きかけるものがないので、疑問を感じている」というものです。
昔と違って今は、ネットやメディアでエンドユーザーは情報を豊富に知っていますので、御社の対策もそうしたものを踏まえた対策にすることが必要かもしれません。
そうじゃないと、来年以降のストレスチェックについても、
「受けても、どうせ大した対策がない」ということになってしまうと、ストレスチェックそのものの存在意義が問われてしまうかも知れません。
実際、そういうことを感じているメンタル担当者は、たくさんおられます。
弊社は、日本で唯一(いや、世界で唯一かも)、企業向けに扁桃体にダイレクトの働きかけて、うつ、メンタル不調の下人である、慢性ストレスを改善していく心理療法を提供している会社、です。
ご関心ある方は、以下のお問合せフォームからお問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/11/29
企業メンタルご担当者様向け情報「ビジネス経験豊富な心理療法士の全社員面談が、うつ、メンタル不調を予防し職場を本当の意味で改善する」
<お知らせ>
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受けました。11/28号に掲載されるようなので、もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/14発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
以前にも書きましたように、弊社では現在、多数の企業から依頼を受けて、ストレスチェック後の全社員面談、または一部の階層に対しての社員面談を行っています。
この面談によって、普段直接上司の前では言えない、普段不都合に感じていることや、もっとこうなれば会社はもっとよくなるのに、ということを聞き出していくのです。
この面談をとおして出てくるのは、人間関係のストレスの話が一番多いのですが、実は、もっとその会社の構造上の課題が浮かび上がります。
たとえば、某会社では若手社員の退職者が多いという現状があって、表面的には人間関係の問題であることがほとんどです。
ストレスチェック後に上司が話しやすいかなどと尋ねている項目がありますが、実はそんな表面的な問題ではないことがほとんどです。
某会社の場合、いろいろヒアリングしてわかったことは、人手不足という問題があり、数年前までは、若手社員は一人の先輩について仕事の手順を学んでいたのですが、忙しいために、今日はA先輩、今日はB先輩、明日はC先輩、の下で作業を手伝うという業務のやり方になっていったのでした。
そこで問題になっていたのが、
「今やっている仕事が全体の一部分の作業しかさせていないことで、トータルで何の役に立っているのか、という視点が欠けた仕事のさせ方をさせてしまうことによる、仕事へのやりがいの低下の問題」です。
数年前は、一人の先輩についていたので、今の仕事はこういうことに役立つんだよとか、これは全体の部分のこういう部分の作業をしているんだよ、という会話が始終あり、そのことで若手は、仕事の全体像がわかることによるやりがいを感じられていたのです。
逆に言うと、やりがいを感じられないからこそ、ストレスに感じやめていくということです。
こういう問題は、いまのストレスチェックでは単に、「先輩が話しやすいかどうか」とか、「先輩が話を聴いてくれるのか」などというような単純化した問題に置き換えられますが、そういう単純な問題ではないことが明らかですよね。
その結果、職場改善策として、部下の話を傾聴する研修を行いましょうとか、コーチングの研修を行いましょうとかになることが多いのではないかと思いますが、そういう問題ではなく、もっと経営視点での人材育成の課題だということです。
こういう面談は、単に話を傾聴する、というようなカウンセリングスキルだけでなく、ビジネスマンとして実際に豊富な経験があり、会社経営に詳しいカウンセラーが、問題の核心をどんどんつき詰めていく質問とアドバイスによって明らかにされていくものなのです。
ストレスチェック後にこういう面談をすることによって、はじめて本当の意味での職場改善、または、生産性向上につながる対策が見えてくるものだと感じています。
ここまでやると経営者としては、お金と手間をかけてストレスチェックをやってよかったと思われるのではないでしょうか。
ご関心ある方は、以下のお問合せフォームからお問合せをどうぞ。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/11/23
企業メンタルご担当者様向け情報「仕事に対するコントロール力を高めるることができると、うつ、メンタル不調の原因である、ストレスを低減する力が向上する」
<お知らせ>
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受けました。11/28号に掲載されるようなので、もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/14発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
今回、義務化されているストレスチェックの政府が推奨している57問の設問の中に、「自分のペースで仕事ができる」かどうかを問う設問があります。
自分がやっている仕事が、急に明日までにやれ、とか、今までやったことがない仕事を突然丸投げされる、とか、さまざなな方針は上のほうで急に決められ自分はいわれたままにやるだけ、とか、そんな立場だとすごいストレスになりますよね。
政府推奨のストレスチェックは、そういう状態にあるのかないのか、と問うているわけです。
カラセックというスウェーデンの心理学者が、「仕事の要求度 コントロールモデル」というものを提唱しています。仕事で要求されるもののレベルが高く、その人がコントロールできる度合いが低いという状態がもっともストレスを感じるということなのです。
これはわかりますよね。
一般的に仕事に対してコントロールできる度合いが高い状態とは、会社の中で地位が高い人ということになると思います。部長や役員などで、仕事を自分自身の裁量で自由にやれる立場にある人は、メンタル不調にはならないでしょう。
一般的に自分が仕事のコントロールができない立場とは、一般的に中間管理職とか、管理職候補のレベルの方々、またはそれよりすこし若い層かもしれません。
ものすごく若い層であれば、上司が守ってくれるでしょう。中間管理職は、会社の売り上げ圧力などがあって、もっとも思い通りにできない人々かもしれません。
では、先ほどの政府推奨の設問の中に合った、「自分のペースで仕事ができるか」に、イエスと答えられるようになるには、もっと昇進させることが近道なのでしょうか。
いえ、そうではありません。結論から言うと、
「本人が自分の気持ちに素直に表現できる自分になることが、仕事のコントロール度を高めるのです」
それはつまり、「助けを求められる」「アドバイスを求めることができる」「納期などを交渉できる」「適度に断れる」「不安があれば、それを表明し対策を求められる」など。
こういうことができると、かなり仕事を自分自身の思った通りに動かすことができるようになるのです。
逆にできないということは、なにも言えないということなので、そうすると周りの仕事の都合の中に巻き込まれていってしまうのです。
基本は、本人のこうした能力を高めることがメンタルを予防することであって、政府推奨の設問では、仕事環境に問題があるようになっているので、これでは会社としても本人の成長を促すことができずに、困ったことになるかもしれません。
仕事のコントロール力を高めることとは、本人の自己表現力を高めることであり、自己表現力」を高めるためには、本人の感受性を安定させ、相手のパワーに影響を受けない自分になることが大切です。
そのためには、脳内の情動の発電装置である、扁桃体の安定を図ることが非常に重要になるのです。
本にの仕事のコントロール力を高めるセルフケア法にご興味ある方は、お問合せフォームからお問い合わせください。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/11/13
企業メンタルご担当者様向け情報「発達しょうがいのことをよく知れば、上手に付き合うことができる」
<お知らせ>
*私の新刊本を読んだ、「プレジデント」というビジネス月刊誌の取材を受けました。11/28号に掲載されるようなので、もしよろしければご覧ください。
★山本潤一のメンタルヘルス新刊本9/14発売!
「不安遺伝子を抑えて、心がす~っとラクになる本」 著者・山本潤一 出版社・秀和システム
リーマンショックのあおりで、仕事をすべて失い、そのショックからうつ状態になった私が復活できた、誰もができるセルフセラピーテクニックを解説!
<以下からブログ本文>
先日、弊社顧問である筑波大学名誉教授・宗像恒次博士が行った「発達しょうがいセミナー」に参加しました。非常に目がうろこの内容だったので、要点をまとめてお伝えします。
最近、企業でもこの問題に頭を悩ませている人事ご担当者も多いと思うので、お役にたつと思います。
まず、発達しょうがいは、日本では「発達障害」という漢字で表記されることが一般的ですが、実はこの名称、大いに疑問が残る名称です。
英語では、Developmental Disorder と書きますが、Disorder には、そもそも「障害」という意味はないのです。無秩序とか、混乱とか、そういう意味です。
宗像博士曰く、発達症、とでも訳すのが正確ではないか、とのこと。一般的な人から見たら「無秩序、混乱」に見えたとしても、たとえばエジソンはADHDだったといわれていますし、ウィンドウズを作ったビル・ゲイツは、自閉症スペクトラムであったと言われています。
これらの方々は、一般的な人から見たら「無秩序、混乱」している変人と見えたかもしれませんが、それは常識的な人から見たら変わった人に見えたから変人というレッテルを貼ったのであって、人々の多様性に対する理解になさから生まれてきている言葉なのです。
今的に言うと、ダイバーシティ(多様性)に対する無理解ですね。
つまり、発達しょうがい、とは個性と呼ぶべきものなのです。それを日本では、発達障害という漢字にしてしまい、いかにも「生涯変えることのできないハンディキャップを背負った人」「一生、医者の世話を受けて治療を受けなければならない人」「障害者」、ような間違った思い込みを多くの方々に広めてしまったのです。
こういう名称は誰が作ったのかわかりませんが、「発達障害」というレッテルを貼られた人が増え、生涯治療が必要と言われる人が増えることで、誰が儲かるのかを考えるとだいたいわかります。
話を戻すと、生涯変えられない性質、というのは全くの誤解です。
たとえば自閉症スペクトラムとは、相手の「目」を直接的に見ることができないことにより、周囲の人から「話を聴いていないように思われる」「反応がよくわからないように見える」「気の利いた反応ができない変わった人」「物事の同時並行処理が苦手」「人との距離感がわからない」
などの個性がその人にあり、周囲もどう扱ったらよいかわからない、ということになります。
相手の目を見れない、というのはここでよく紹介しているように、脳内の情動の発電装置である、扁桃体(へんとうたい)が過剰に反応してしまう、ということです。
扁桃体には、相手の顔に敏感に反応してしまう、顔反応性細胞がありこれが激しく反応して恐怖や不安やその他、さまざまなマイナス感情を発生させてしまうのです。
ほかのところで発達障害と言われ続けてきた人でも、私たちのところで扁桃体反応を安定させる心理療法を行うことで、相手の顔を見れるようになり、人との距離感が元に戻り、自閉症スペクトラムを診断する心理テストの得点が、標準値に戻った人はたくさんいるのです。
「障害」という名称は不適切だと思います。
多くの企業では、発達しょうがいと呼ばれている方々をどのように扱ったらよいのか、よくわからないというということもあるでしょう。
こういう方々との付き合い方の本や、そういうことを教えてくれる団体なども最近出てきていますが、一番見落とされているなと感じることが一つあります。それは、
「扁桃体にかんする配慮がない」
ということです。自閉症スペクトラムの方が相手の目を見るのを避けるのは、相手の表情を見てしまうと扁桃体が大暴走して、パニックが起きてしまうからです。
ADHDの人は、相手の表情に激しく反応して行動がしっちゃかめっちゃかになります。
特に自閉症スペクトラムの人には、目を見るコミュニケーションを期待してはいけないのです。このことがよく理解されていないために、一般に自閉症スペクトラムの人に対して行われる療育やソーシャルスキルトレーニングなどでは、相手の顔をよく見てコミュニケーションをするというような、訓練がなされることがあります。
これは逆効果で、扁桃体のことが知られていないために引き起こされる誤解です。
もちろん扁桃体興奮を鎮静化するという心理療法を行った後だったら大丈夫ですよ。でも、その前では逆効果です。
このことをよく理解したうえで、こういった方々と上手に付き合って生産性を高めるのコツがさまざまにあるのです。
ご興味ある方は、お問合せフォームからお問い合わせください。
弊社が行っている心理療法は、厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では、ヘルスカウンセリングと紹介され、数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と書かれているものです。
健康心理学に基づく「社員のあるがままの自分を生かす働き方を引き出す、面談、ラインケアスキル、セルフケアスキル習得教育、個人カウンセリング、、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。
既存のメンタル対策と組み合わせ、某上場企業では3年半、初回うつ休職者の再発0%の結果に貢献しました。
詳しく知りたい方は、下記お問合せフォームから資料請求をどうぞ。
2016/11/06
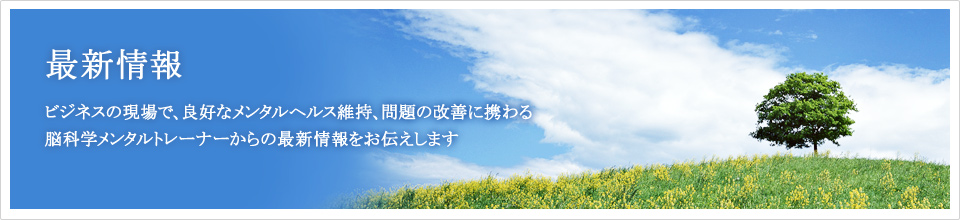
 前へ
前へ